No.272, No.271, No.270, No.269, No.268, No.267, No.266[7件]
無題/ホンイサ
※ユロージヴィホンルがいる世界線 暗い
――これは、イサンの知らない「イサン」の話。
N社に連行されてすぐ、煤汚れた身体を清めるべく、クボに勧められた湯浴み――辞退したところで、無理矢理にでも浴槽に沈められるだろう。抵抗するにも、今はもう疲れた――を済ませようと衣服に手をかけたところで、ふとボトムスのポケットに不自然な凹凸があることに気付く。手を差し込んでみると、そこに入っていたのは一本のロリポップだった。
「こは――」目を惹かれるような包装に包まれた――記憶に残るそれは、目の当たりにしているものよりもずっと色褪せてはいたけれど――その菓子を、自分は知っている。
「あの青年――ホンルからもらった飴玉だな」
白い四角形の中、己に語りかけてくる唯一の声に、自ずと注意は鏡へと向けられた。元々手鏡だったそれは幾重にも増幅され、今では姿見ほどのサイズまで引き伸ばされた鏡面に映し出された、燦爛とした翼を背に抱いた、自身と鏡合わせの見目をした「イサン」の左手。
「……彼に別れを告げられなかったこと、後悔してるんじゃないか?」
「…………」
これまでのスーツ姿から、清潔な白衣に装いを改めたサンイが、眉根を下げながら訊ねる。心から気遣うような、最も信を置く彼の言の葉にすら、イサンは沈黙を返答とした。
ホンルという不思議な青年と出会ったのは、まだT社で身を潜めることなく活動していた頃にまで遡る。必要な部品の調達に向かう道中、奇しくも殺人事件の「犯人」として槍玉に挙げられてしまったイサンの前に現れたのが、全ての始まりだった。探偵を自称するその男は、イサンを犯人であると疑う一方で、その疑いを晴らすために取引を持ちかけ、捜査にも協力を惜しまなかった。ちぐはぐな行動と理由について、問うたこともあったが――
「う~ん……容疑者を自分の監視下に置くため……っていう理由もありますけど、本当にイサンさんが犯人じゃないのだとしたら、それはそれで興味深い展開だと思いませんか?」
などと破顔一笑で嘯くものだから、当初は開いた口が塞がらなかった。
事件が無事に解決して以降も、彼との交流が途切れることはなかった。彼に連れられ数日ぶりの食事を摂ったり、捜査に関する意見を求められたり――時には、飯代を人質にしてそのまま事件捜査に連れ出されたことだって、一度や二度ではない。
これまで九人会以外の交流をほとんど持たなかったイサンにとって、困惑こそあったものの、この出会いは決して悪いものではなかった。信頼もしていた――と思う。それでも、彼には結局自身の正体を明かせずじまいだった。今頃きっと、自分がT社を騒がせた悪名高い九人会の一員である事実を知り、さぞ失望していることだろう。
「……そなたが案ずることはあらず」
「だが……イサン……お前、彼のことが――」
なおも憂いの消えぬサンイの面持ちに、イサンはこれ以上の言葉を遮るようにして、唇に笑みを象りながら、頭を振る。自分の真意など、鏡写しの彼に隠す必要はない――隠したところで、彼には全てお見通しだろうから――たとえそうだとして、今更後悔したからといって何かが変わるわけではない。自由に羽ばたくための翼を持たぬ自分に、この鳥籠から抜け出す術はない。この四角形から外を知ることなく――サンイならば、自分の代わりに外の世界を見てきてくれるだろう――さながら羽を切られた鶏のように、利用価値のある限りは甲斐甲斐しく飼育され、やがては力尽きる運命だから。
――何よりも、一言も告げずに消息を絶った自分に、愛想を尽かして余りあるであろう彼に会うこと自体が――その事実を、他でもない彼によって突きつけられるのが――怖かった。
伏せた視線が、再びロリポップに落ちる。共に過ごしたほとんどの時間、咥えていたそれは、一体どのような色をしているのだろう。拙い指遣いで破り取った包装から、姿を現した飴玉は眩暈がするほど鮮烈な青色をしていて――かつて、朋と見上げていた故郷の空もこのくらい鮮やかだった――思いがけず、目を奪われた。ずっと、知らなかった。
知りたかったことは、まだまだ山ほどある。ホンルの髪と瞳は何色だったのだろう。よく観察してみると、瞳はそれぞれ異なる彩りを成していたように見えたが――セピア色をした景色の中でも、左目は燦爛と煌めいてきた気がする――もしやすると、この飴のように綺麗な色をしていたのかもしれない。何とはなしだが、イサンには確信があった。
もし――T社から離れたホンルと、またどこかで巡り会うようなことがあれば、彼だけが持つ本当の色を知れるだろうか。いや、寧ろ自身の無個性な彩色を見てがっかりされるやも――思考を止める。嫌というほど思い知らされただろう――奇跡など、起きやしないと。
記憶に焼きつくまで見つめていたそれを、おもむろに咥える。口いっぱいに広がるケミカルな甘味と芳香――初めてホンルに口へと放り込まれた時、あまり好みではないと告げたことを思い出す――慣れると結構病みつきになると、彼は飄々と笑っていたけれど――自分には刺激が強い甘露を、それでもしばし舌で転がし、味わい、彼との思い出に思いを馳せる。
きっとホンルに出会えた自分は、全ての「イサン」の中でも特に幸福であったに違いない。
だから――たとえ彼に会う資格が、自分にはなくとも――願うだけでも――
かりりと音を立てて、彼との唯一の思い出を噛み砕く。
――彼が、末永く平安であらんことを。
畳む
#LCB61 #ユロージヴィ
※ユロージヴィホンルがいる世界線 暗い
――これは、イサンの知らない「イサン」の話。
N社に連行されてすぐ、煤汚れた身体を清めるべく、クボに勧められた湯浴み――辞退したところで、無理矢理にでも浴槽に沈められるだろう。抵抗するにも、今はもう疲れた――を済ませようと衣服に手をかけたところで、ふとボトムスのポケットに不自然な凹凸があることに気付く。手を差し込んでみると、そこに入っていたのは一本のロリポップだった。
「こは――」目を惹かれるような包装に包まれた――記憶に残るそれは、目の当たりにしているものよりもずっと色褪せてはいたけれど――その菓子を、自分は知っている。
「あの青年――ホンルからもらった飴玉だな」
白い四角形の中、己に語りかけてくる唯一の声に、自ずと注意は鏡へと向けられた。元々手鏡だったそれは幾重にも増幅され、今では姿見ほどのサイズまで引き伸ばされた鏡面に映し出された、燦爛とした翼を背に抱いた、自身と鏡合わせの見目をした「イサン」の左手。
「……彼に別れを告げられなかったこと、後悔してるんじゃないか?」
「…………」
これまでのスーツ姿から、清潔な白衣に装いを改めたサンイが、眉根を下げながら訊ねる。心から気遣うような、最も信を置く彼の言の葉にすら、イサンは沈黙を返答とした。
ホンルという不思議な青年と出会ったのは、まだT社で身を潜めることなく活動していた頃にまで遡る。必要な部品の調達に向かう道中、奇しくも殺人事件の「犯人」として槍玉に挙げられてしまったイサンの前に現れたのが、全ての始まりだった。探偵を自称するその男は、イサンを犯人であると疑う一方で、その疑いを晴らすために取引を持ちかけ、捜査にも協力を惜しまなかった。ちぐはぐな行動と理由について、問うたこともあったが――
「う~ん……容疑者を自分の監視下に置くため……っていう理由もありますけど、本当にイサンさんが犯人じゃないのだとしたら、それはそれで興味深い展開だと思いませんか?」
などと破顔一笑で嘯くものだから、当初は開いた口が塞がらなかった。
事件が無事に解決して以降も、彼との交流が途切れることはなかった。彼に連れられ数日ぶりの食事を摂ったり、捜査に関する意見を求められたり――時には、飯代を人質にしてそのまま事件捜査に連れ出されたことだって、一度や二度ではない。
これまで九人会以外の交流をほとんど持たなかったイサンにとって、困惑こそあったものの、この出会いは決して悪いものではなかった。信頼もしていた――と思う。それでも、彼には結局自身の正体を明かせずじまいだった。今頃きっと、自分がT社を騒がせた悪名高い九人会の一員である事実を知り、さぞ失望していることだろう。
「……そなたが案ずることはあらず」
「だが……イサン……お前、彼のことが――」
なおも憂いの消えぬサンイの面持ちに、イサンはこれ以上の言葉を遮るようにして、唇に笑みを象りながら、頭を振る。自分の真意など、鏡写しの彼に隠す必要はない――隠したところで、彼には全てお見通しだろうから――たとえそうだとして、今更後悔したからといって何かが変わるわけではない。自由に羽ばたくための翼を持たぬ自分に、この鳥籠から抜け出す術はない。この四角形から外を知ることなく――サンイならば、自分の代わりに外の世界を見てきてくれるだろう――さながら羽を切られた鶏のように、利用価値のある限りは甲斐甲斐しく飼育され、やがては力尽きる運命だから。
――何よりも、一言も告げずに消息を絶った自分に、愛想を尽かして余りあるであろう彼に会うこと自体が――その事実を、他でもない彼によって突きつけられるのが――怖かった。
伏せた視線が、再びロリポップに落ちる。共に過ごしたほとんどの時間、咥えていたそれは、一体どのような色をしているのだろう。拙い指遣いで破り取った包装から、姿を現した飴玉は眩暈がするほど鮮烈な青色をしていて――かつて、朋と見上げていた故郷の空もこのくらい鮮やかだった――思いがけず、目を奪われた。ずっと、知らなかった。
知りたかったことは、まだまだ山ほどある。ホンルの髪と瞳は何色だったのだろう。よく観察してみると、瞳はそれぞれ異なる彩りを成していたように見えたが――セピア色をした景色の中でも、左目は燦爛と煌めいてきた気がする――もしやすると、この飴のように綺麗な色をしていたのかもしれない。何とはなしだが、イサンには確信があった。
もし――T社から離れたホンルと、またどこかで巡り会うようなことがあれば、彼だけが持つ本当の色を知れるだろうか。いや、寧ろ自身の無個性な彩色を見てがっかりされるやも――思考を止める。嫌というほど思い知らされただろう――奇跡など、起きやしないと。
記憶に焼きつくまで見つめていたそれを、おもむろに咥える。口いっぱいに広がるケミカルな甘味と芳香――初めてホンルに口へと放り込まれた時、あまり好みではないと告げたことを思い出す――慣れると結構病みつきになると、彼は飄々と笑っていたけれど――自分には刺激が強い甘露を、それでもしばし舌で転がし、味わい、彼との思い出に思いを馳せる。
きっとホンルに出会えた自分は、全ての「イサン」の中でも特に幸福であったに違いない。
だから――たとえ彼に会う資格が、自分にはなくとも――願うだけでも――
かりりと音を立てて、彼との唯一の思い出を噛み砕く。
――彼が、末永く平安であらんことを。
畳む
#LCB61 #ユロージヴィ




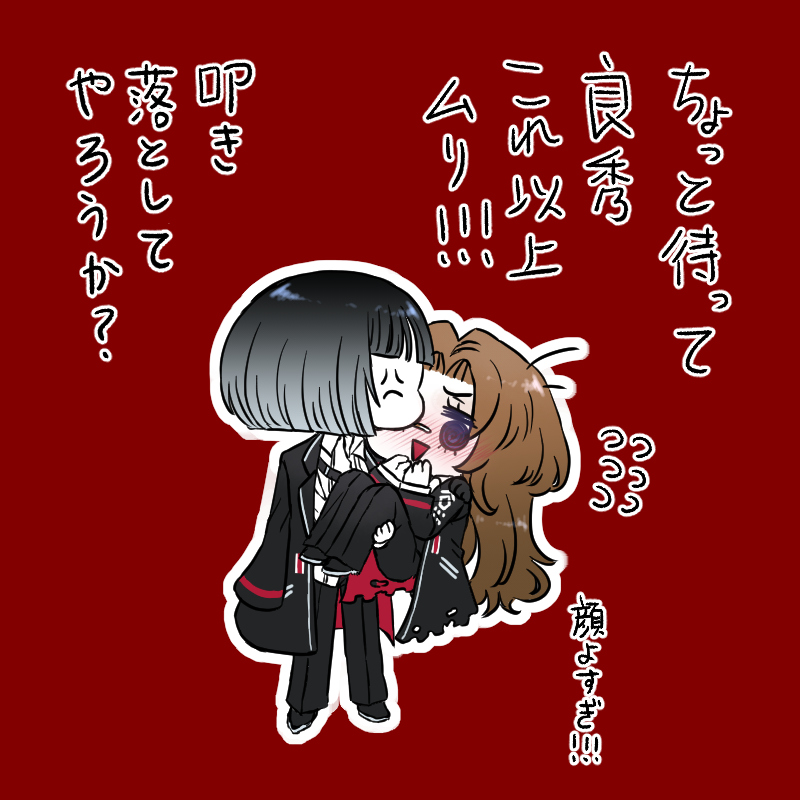

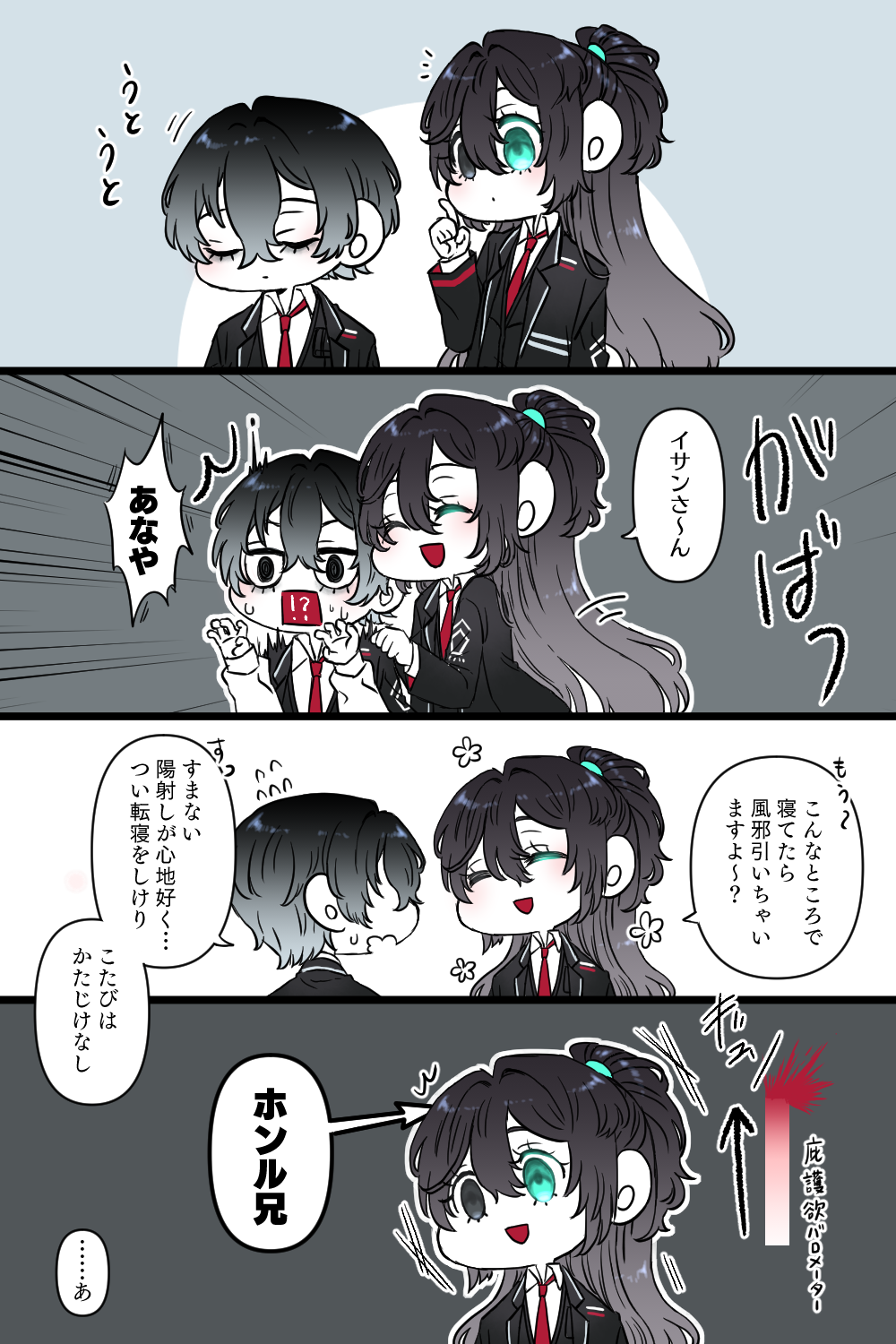
それよりも東部に派遣されるってことは8章あたりでリウ協会のフィクサーが出てくるんです??
イサンが東部に派遣される=原典先生が「東」京に行ったことを示唆しているのではないかという考察を見かけて、末路まで考えるとめちゃくちゃ頭を抱えた。
#リウ協会