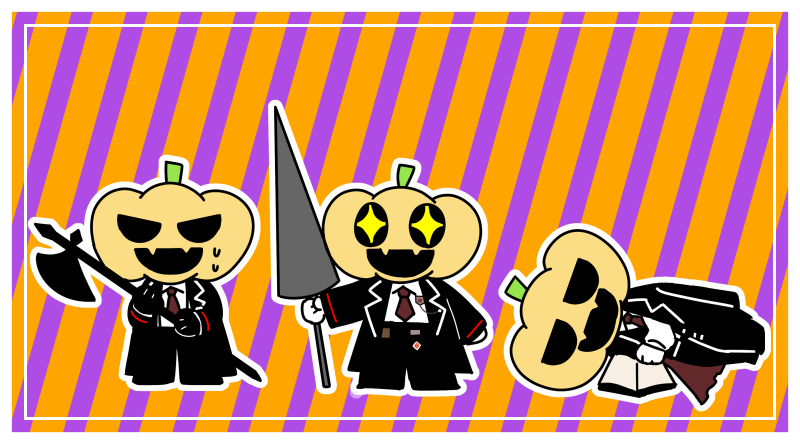#LCB0102 #セブン協会
#LCB0102 #セブン協会
2024年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する
 #LCB0102 #セブン協会
#LCB0102 #セブン協会
永遠にあなたのもの/ホンイサ
K社と壇香梅 ※メリバ
「一緒に、ここから逃げましょう」
いつもと何ら変わらぬ柔らかな声色。それが紡がれるたび、皹割れた口唇から咳と共に無数の赤い線が重力に従うようにして零れ落ちていく様を、ただ茫洋と眺めていた。
「あなたと一緒なら、どこだって良いです」
血風に彩られた戦場にて――そして、気まぐれに訪れる安穏としたひとときにおいて――爛々と煌めいていたはずの双眸がふと細められる。その拍子にだろうか。長い睫毛の縁取る眼瞼から、止め処ない雨垂れの如く流れるそれが、しっかと掻き抱いて離さぬ腕の中、衣を赤く汚したとして、引き剥がそうという思考が過ぎることはついになかった。
「あなたと一緒なら、裏路地だって……外郭だって構わない」
咳嗽混じりの言の葉は、もはや聞くに耐えないほど弱々しく、痛ましさを伴いながら鼓膜を叩く。
――そなたの言の葉なぞ、ゆかしからず。
そう、突き放してしまえばこれまでの奇妙な関係は全て清算されるだろう。そうして彼がK社に戻り、適切な処置を受けられたならば、身体の崩壊も止まるはずだ――いや、待て。何故彼の身を案じているのだ、私は。
彼の刃に斃れた皆の顔は、今でも鮮明に思い出せる。これまでに多くの同胞を殺めてきた男だ。皮肉を並べることにも、傷付いた顔を見ることにも疾うに慣れていたし、それが当然の報いであると信じて疑わなかった。
刹那、鉄の匂いを伴いながら唇へと触れた幽きぬくもりに、現実に引き戻される。
眼前にある男の笑顔は、酷く穏やかだった。
「――僕が、あなたを守りますから」
確かな響きをもって、絞り出された音を最後に、彼はもう何も語らなかった。宝石のように煌めいていたはずの双眸からは光を失い、ぐったりと撓垂れかかる恵体を、緩慢な動作で抱き締める。あえかに繰り返される呼吸も、やがては止まることだろう。
白く染まりゆく頭で、彼から齎された言葉を思い返す。
一緒にここから逃げよう、一緒ならばどこだって構わない――は、と笑声が漏れた。いくら綺麗事を連ねたところで、結局は自分を置いていこうとしているではないか。
「……げに、強ちなる男よ」
吐き捨てるようにして、口を衝いて出た恨み言。
しかし、心は酷く穏やかだった。
身体の奥底で、何かが綻ぶような感覚があった。
技術の解放を掲げたその瞬間から、安らかなる最期が訪れることはないと覚悟していた。
今はどうだろう。おもむろに顔を上げる。
かつて故郷で見た、どこまでも広がっていると信じて疑わなかった、晴れ渡る青い空の下。
え辛い花の香に身も心も包まれながら。
そうして、そこで意識は途切れた。
畳む
#LCB61 #技術解放連合 #K社
K社と壇香梅 ※メリバ
「一緒に、ここから逃げましょう」
いつもと何ら変わらぬ柔らかな声色。それが紡がれるたび、皹割れた口唇から咳と共に無数の赤い線が重力に従うようにして零れ落ちていく様を、ただ茫洋と眺めていた。
「あなたと一緒なら、どこだって良いです」
血風に彩られた戦場にて――そして、気まぐれに訪れる安穏としたひとときにおいて――爛々と煌めいていたはずの双眸がふと細められる。その拍子にだろうか。長い睫毛の縁取る眼瞼から、止め処ない雨垂れの如く流れるそれが、しっかと掻き抱いて離さぬ腕の中、衣を赤く汚したとして、引き剥がそうという思考が過ぎることはついになかった。
「あなたと一緒なら、裏路地だって……外郭だって構わない」
咳嗽混じりの言の葉は、もはや聞くに耐えないほど弱々しく、痛ましさを伴いながら鼓膜を叩く。
――そなたの言の葉なぞ、ゆかしからず。
そう、突き放してしまえばこれまでの奇妙な関係は全て清算されるだろう。そうして彼がK社に戻り、適切な処置を受けられたならば、身体の崩壊も止まるはずだ――いや、待て。何故彼の身を案じているのだ、私は。
彼の刃に斃れた皆の顔は、今でも鮮明に思い出せる。これまでに多くの同胞を殺めてきた男だ。皮肉を並べることにも、傷付いた顔を見ることにも疾うに慣れていたし、それが当然の報いであると信じて疑わなかった。
刹那、鉄の匂いを伴いながら唇へと触れた幽きぬくもりに、現実に引き戻される。
眼前にある男の笑顔は、酷く穏やかだった。
「――僕が、あなたを守りますから」
確かな響きをもって、絞り出された音を最後に、彼はもう何も語らなかった。宝石のように煌めいていたはずの双眸からは光を失い、ぐったりと撓垂れかかる恵体を、緩慢な動作で抱き締める。あえかに繰り返される呼吸も、やがては止まることだろう。
白く染まりゆく頭で、彼から齎された言葉を思い返す。
一緒にここから逃げよう、一緒ならばどこだって構わない――は、と笑声が漏れた。いくら綺麗事を連ねたところで、結局は自分を置いていこうとしているではないか。
「……げに、強ちなる男よ」
吐き捨てるようにして、口を衝いて出た恨み言。
しかし、心は酷く穏やかだった。
身体の奥底で、何かが綻ぶような感覚があった。
技術の解放を掲げたその瞬間から、安らかなる最期が訪れることはないと覚悟していた。
今はどうだろう。おもむろに顔を上げる。
かつて故郷で見た、どこまでも広がっていると信じて疑わなかった、晴れ渡る青い空の下。
え辛い花の香に身も心も包まれながら。
そうして、そこで意識は途切れた。
畳む
#LCB61 #技術解放連合 #K社
あなたの理由になりたかった/ホンイサ
K社と壇香梅
開け放たれた障子から射し込む陽光へとこの身を晒す。耳に蝟集するのは、姦しいばかりの都市の喧騒であればすぐに掻き消されてしまいそうな木々のささめき、小鳥の囀り、そして志を同じくする同朋達の語らい。
緩やかに流れゆく時間に身を委ね、羽を伸ばすのは果たしていつぶりだろうか。大義の下、これまでに多くの屍を積み重ねてきた。これまでに流した、そして流された血で彩られた異常と呼ぶべき――けれど、もはや麗しさすら見出していたその道をひた進む我々には分不相応なほど、酷く穏やかで静謐なひととき。
幽けき音に耳を傾けながら、陽射しの眩さに思わず細めた目をゆるりと伏せる。たまには、こうして午睡に耽るのも悪くないのかも知れない。
「イサンさん、質問したいことがあるんですけど~」
――すぐ傍らで呑気な音が落とされたかと思えば、次いで胡座を組んだ膝へとのしかかる重みに閉ざしかけていた瞼を堪らず開いた。眼前には、瞬く星夜を梳かしたような豊かな黒髪。そして、炳として此方を見つめる翡翠と黒曜石。仮に乗せるとして、それが愛くるしい小動物であればどれほど良かったことか。
「重し。離れたまえ、疾く」
「え~?」
まるでそれが当然の権利であるかのように、さも自然に膝を枕にして寛いでいる男を扇で押し返そうとするも、微動だにしないどころか当の本人は形の良い唇を尖らせるばかりで一向に動こうとする気配はない。鍛え上げられた恵体を強固なボディースーツで鎧った男が、あたかも愛猫の如き振る舞いでじゃれついてくる様は――とはいえ、実のところ髪の触り心地は絹糸めいて存外に悪くない。悪くないが、決して彼の前で口にしてやるものか――悪夢以外の何物でもないだろうに。いや、まずそれよりもこの男が当たり前のように敵勢力の本拠地へと容易く足を踏み入れている時点で度し難い異常事態なのだが。
「僕の話し相手になってくれるだけで良いんです~。だって、こんなに心地好い日和でしょう? 何か話してないとこのままうっかり眠っちゃいそうで~」
「ふん、おのがままに眠るべからむ」
「それが出来たらどんなに良いか~……研究員さんの話だと、夢見ひとつで崩壊に繋がるらしいので、僕達摘出職職員に睡眠はご法度なんですよね」
「…………」
男の口調は同情を誘うような哀しげなそれでも、自身の身の上を呪うような恨めしげなそれでもない。ただいつものように人好きのする微笑を浮かべながら、あっけらかんと告げるその様子に、自ずと視線は下がっていった。
再び訪れた沈黙を同意であると判断したのだろう。床に転がる花弁を指先で弄びながら、眼前の男は笑みを深めるその唇を開いた。
「イサンさん達は、この世からあらゆる技術を消し去るために行動してるんですよね?」
「……さりとし、何なりや?」
いかなる技術の存在しなかった、全てが一層輝いて見えた過去に戻る――自身の理念とは多少の相違はあるといえど、概ね間違ってはいない。
「僕、少し気になったんです。『技術の解放』が大義だとして、そうだとしたらその解放すべき『技術』というものも、その自由を望んでいるのかな――って」
まるで技術が意思を持つかのような口ぶりで、あどけない好奇心に塗れた言の葉が、眼差しが、一心に己へと向けられる。
「あ、おかしなことを言う奴だと思ったでしょう? AIだって、もしかすると人間よりも人間らしい思考を持っているとも知れないじゃないですか。同じく人間によって見出された技術が、彼らなりの意思を持っていたって何ら不思議ないと思いますけど~」
よほど――それこそ狐にでもつままれたような顔をしていたのだろうか。くつくつと喉を鳴らした男は伸びをするように、膝の上で身を捩る。しゃらり、しゃらと、長い髪が音を立てて床へと零れ落ちた。
「――それで、イサンさんはどう思います?」
色の異なる双眸が覗き込むように見上げてくる。思いつきのように、突として齎された問いかけに対して自分が応えてやる義理などないし、そのことは彼も織り込み済みであることを疑う余地はない。
しかし、その心とは裏腹に、意識は思惟に沈んでいく。
まず過ぎるのは、さる翼の「鑑賞室」。人々へ癒しを与える星の子のためだけに上映される悲劇的視聴覚飼料。
次いで過ぎったのは、さる巣に構える屋敷。嵐の吹き荒ぶその地下で繰り広げられるおぞましい人体実験。
どちらも自分自身が目の当たりにしたわけではない。いつか鏡越しに見た、幾つもの可能性のいずれかで起きたやも知れぬ、もしもでしかない光景。――しかし、もしも唾棄すべきそれらに用いられた「技術」自身が、喜んでその身を差し出しているのだとしたら――
花枝を手折るかの如き、乾いた音が響いた。
「あちゃぁ……」
嘆息にも似た声を漏らした男が、壊れ物でも扱うかのように恭しい手つきで取られた右手。逸る心臓から送り込まれる、滾るような血潮。どっと噴き出す汗が気持ち悪い。乱れかけた思考を律し、遅々とした動作で動かした視線の先で、ようやく親骨の折れた扇に気付いた。
「派手にやりましたね~。怪我、痛くありませんか?」
折れた拍子に、木片が指に食い込んだのだろう。破れた皮膚から珠のような血が滲んでいく様を、茫洋と眺めながら。
「……私は、そなたが憎し」
突拍子もなく口を衝いて出た言葉に――おそらく、傷を診ようとしたのだろう。自身に伸ばされた男の手が止まった。見開かれた瞳が酷く揺らいでいる――至極当然だと言い聞かせる。彼等摘出職職員によって、今までどれほどの同胞が手にかけられたことか。己を気遣うような真似をするこの男とて、戦場に投入されれば息をするように得物を振るい、唇に変わらぬ笑みを湛えたまま、つい先刻まで親しげに語りかけていたであろう者達をいとも容易く崩壊させていく。
「……はい。勿論、知ってます」
この男がどういった経緯でK社へと入職するに至ったのかは概ね把握している――とはいえ、彼が聞きもしないのに話したからだが――故にこそ、理解出来なかった。
仲間を守ることさえ出来ず、呪いの言葉を吐き散らすことしか出来ぬ取るに足らぬ存在など、嗤って一蹴すれば良いだろうのに。
何故、彼は彼自身に課せられた理不尽に対して怒りを顕わにしないのか。
何故――彼は、こんなにも哀しげに微笑むだけなのか。
「そして――そなたをさに変えにけるK社もまた、さなり」
先とは異なる色を宿して瞠目した二つの宝珠が、己を凝視していることなど気にも留めず、続ける。
「うち出でしばかりの技術は純粋で……かくて、無知なり」
まるで、その技術を使用する当人を映し出す鏡のように。
かの翼の特異点によって齎されるのが慈雨の如き癒しであったとして、その癒しを得るために――硝子管の中でしか生きられぬ兵士を作り出すために、そして汚らわしい私利私欲のために、この世に生まれ出でた尊き技術が凌辱されるというならば。
「私は、技術の全てを灰燼に帰さん」
技術の意思など関係なく。
それが技術の生まれる瞬間を見届けた時に感じた、打ち震えるような純粋な喜びを知る者としての、自分に出来る責務だ。
「これで満足せりや?」
「……あはっ。ちょっと身勝手が過ぎる回答じゃないですか~、それ?」鈴を転がすような、玲瓏な笑声を上げながら続ける男の目には、一片の揶揄も嘲笑も孕んでいない。「でも、ありがとうございます。イサンさんが僕の代わりに気を揉んでくれるだなんて、少し意外だったかも」
「自惚れも大概にしたまえ」
「え~っ。明らかにそういった意味を含んでましたよね、あの言葉!」
不意に起き上がったかと思えば、遠慮のない膂力でこの身を抱き竦めてくるのだから息苦しくて仕方がない。このまま己を抱き潰して息の根を止める心算なのだろうか、この男は。
「……でも、僕だってこの職に就いて嫌なことばかりじゃないんですよ? だって――」
僕が摘出職職員じゃなかったら、イサンさんに会えることなんて、一生なかったでしょうから。
睦言を紡ぐかのように、耳元で囁かれた密やかな声。寸秒の沈黙の後、その頭を折れた扇で叩いてやった手に、不自然に汗が滲んでいたのは暑苦しかったせいだと自分に言い聞かせた。
畳む
#LCB61 #技術解放連合 #K社
K社と壇香梅
開け放たれた障子から射し込む陽光へとこの身を晒す。耳に蝟集するのは、姦しいばかりの都市の喧騒であればすぐに掻き消されてしまいそうな木々のささめき、小鳥の囀り、そして志を同じくする同朋達の語らい。
緩やかに流れゆく時間に身を委ね、羽を伸ばすのは果たしていつぶりだろうか。大義の下、これまでに多くの屍を積み重ねてきた。これまでに流した、そして流された血で彩られた異常と呼ぶべき――けれど、もはや麗しさすら見出していたその道をひた進む我々には分不相応なほど、酷く穏やかで静謐なひととき。
幽けき音に耳を傾けながら、陽射しの眩さに思わず細めた目をゆるりと伏せる。たまには、こうして午睡に耽るのも悪くないのかも知れない。
「イサンさん、質問したいことがあるんですけど~」
――すぐ傍らで呑気な音が落とされたかと思えば、次いで胡座を組んだ膝へとのしかかる重みに閉ざしかけていた瞼を堪らず開いた。眼前には、瞬く星夜を梳かしたような豊かな黒髪。そして、炳として此方を見つめる翡翠と黒曜石。仮に乗せるとして、それが愛くるしい小動物であればどれほど良かったことか。
「重し。離れたまえ、疾く」
「え~?」
まるでそれが当然の権利であるかのように、さも自然に膝を枕にして寛いでいる男を扇で押し返そうとするも、微動だにしないどころか当の本人は形の良い唇を尖らせるばかりで一向に動こうとする気配はない。鍛え上げられた恵体を強固なボディースーツで鎧った男が、あたかも愛猫の如き振る舞いでじゃれついてくる様は――とはいえ、実のところ髪の触り心地は絹糸めいて存外に悪くない。悪くないが、決して彼の前で口にしてやるものか――悪夢以外の何物でもないだろうに。いや、まずそれよりもこの男が当たり前のように敵勢力の本拠地へと容易く足を踏み入れている時点で度し難い異常事態なのだが。
「僕の話し相手になってくれるだけで良いんです~。だって、こんなに心地好い日和でしょう? 何か話してないとこのままうっかり眠っちゃいそうで~」
「ふん、おのがままに眠るべからむ」
「それが出来たらどんなに良いか~……研究員さんの話だと、夢見ひとつで崩壊に繋がるらしいので、僕達摘出職職員に睡眠はご法度なんですよね」
「…………」
男の口調は同情を誘うような哀しげなそれでも、自身の身の上を呪うような恨めしげなそれでもない。ただいつものように人好きのする微笑を浮かべながら、あっけらかんと告げるその様子に、自ずと視線は下がっていった。
再び訪れた沈黙を同意であると判断したのだろう。床に転がる花弁を指先で弄びながら、眼前の男は笑みを深めるその唇を開いた。
「イサンさん達は、この世からあらゆる技術を消し去るために行動してるんですよね?」
「……さりとし、何なりや?」
いかなる技術の存在しなかった、全てが一層輝いて見えた過去に戻る――自身の理念とは多少の相違はあるといえど、概ね間違ってはいない。
「僕、少し気になったんです。『技術の解放』が大義だとして、そうだとしたらその解放すべき『技術』というものも、その自由を望んでいるのかな――って」
まるで技術が意思を持つかのような口ぶりで、あどけない好奇心に塗れた言の葉が、眼差しが、一心に己へと向けられる。
「あ、おかしなことを言う奴だと思ったでしょう? AIだって、もしかすると人間よりも人間らしい思考を持っているとも知れないじゃないですか。同じく人間によって見出された技術が、彼らなりの意思を持っていたって何ら不思議ないと思いますけど~」
よほど――それこそ狐にでもつままれたような顔をしていたのだろうか。くつくつと喉を鳴らした男は伸びをするように、膝の上で身を捩る。しゃらり、しゃらと、長い髪が音を立てて床へと零れ落ちた。
「――それで、イサンさんはどう思います?」
色の異なる双眸が覗き込むように見上げてくる。思いつきのように、突として齎された問いかけに対して自分が応えてやる義理などないし、そのことは彼も織り込み済みであることを疑う余地はない。
しかし、その心とは裏腹に、意識は思惟に沈んでいく。
まず過ぎるのは、さる翼の「鑑賞室」。人々へ癒しを与える星の子のためだけに上映される悲劇的視聴覚飼料。
次いで過ぎったのは、さる巣に構える屋敷。嵐の吹き荒ぶその地下で繰り広げられるおぞましい人体実験。
どちらも自分自身が目の当たりにしたわけではない。いつか鏡越しに見た、幾つもの可能性のいずれかで起きたやも知れぬ、もしもでしかない光景。――しかし、もしも唾棄すべきそれらに用いられた「技術」自身が、喜んでその身を差し出しているのだとしたら――
花枝を手折るかの如き、乾いた音が響いた。
「あちゃぁ……」
嘆息にも似た声を漏らした男が、壊れ物でも扱うかのように恭しい手つきで取られた右手。逸る心臓から送り込まれる、滾るような血潮。どっと噴き出す汗が気持ち悪い。乱れかけた思考を律し、遅々とした動作で動かした視線の先で、ようやく親骨の折れた扇に気付いた。
「派手にやりましたね~。怪我、痛くありませんか?」
折れた拍子に、木片が指に食い込んだのだろう。破れた皮膚から珠のような血が滲んでいく様を、茫洋と眺めながら。
「……私は、そなたが憎し」
突拍子もなく口を衝いて出た言葉に――おそらく、傷を診ようとしたのだろう。自身に伸ばされた男の手が止まった。見開かれた瞳が酷く揺らいでいる――至極当然だと言い聞かせる。彼等摘出職職員によって、今までどれほどの同胞が手にかけられたことか。己を気遣うような真似をするこの男とて、戦場に投入されれば息をするように得物を振るい、唇に変わらぬ笑みを湛えたまま、つい先刻まで親しげに語りかけていたであろう者達をいとも容易く崩壊させていく。
「……はい。勿論、知ってます」
この男がどういった経緯でK社へと入職するに至ったのかは概ね把握している――とはいえ、彼が聞きもしないのに話したからだが――故にこそ、理解出来なかった。
仲間を守ることさえ出来ず、呪いの言葉を吐き散らすことしか出来ぬ取るに足らぬ存在など、嗤って一蹴すれば良いだろうのに。
何故、彼は彼自身に課せられた理不尽に対して怒りを顕わにしないのか。
何故――彼は、こんなにも哀しげに微笑むだけなのか。
「そして――そなたをさに変えにけるK社もまた、さなり」
先とは異なる色を宿して瞠目した二つの宝珠が、己を凝視していることなど気にも留めず、続ける。
「うち出でしばかりの技術は純粋で……かくて、無知なり」
まるで、その技術を使用する当人を映し出す鏡のように。
かの翼の特異点によって齎されるのが慈雨の如き癒しであったとして、その癒しを得るために――硝子管の中でしか生きられぬ兵士を作り出すために、そして汚らわしい私利私欲のために、この世に生まれ出でた尊き技術が凌辱されるというならば。
「私は、技術の全てを灰燼に帰さん」
技術の意思など関係なく。
それが技術の生まれる瞬間を見届けた時に感じた、打ち震えるような純粋な喜びを知る者としての、自分に出来る責務だ。
「これで満足せりや?」
「……あはっ。ちょっと身勝手が過ぎる回答じゃないですか~、それ?」鈴を転がすような、玲瓏な笑声を上げながら続ける男の目には、一片の揶揄も嘲笑も孕んでいない。「でも、ありがとうございます。イサンさんが僕の代わりに気を揉んでくれるだなんて、少し意外だったかも」
「自惚れも大概にしたまえ」
「え~っ。明らかにそういった意味を含んでましたよね、あの言葉!」
不意に起き上がったかと思えば、遠慮のない膂力でこの身を抱き竦めてくるのだから息苦しくて仕方がない。このまま己を抱き潰して息の根を止める心算なのだろうか、この男は。
「……でも、僕だってこの職に就いて嫌なことばかりじゃないんですよ? だって――」
僕が摘出職職員じゃなかったら、イサンさんに会えることなんて、一生なかったでしょうから。
睦言を紡ぐかのように、耳元で囁かれた密やかな声。寸秒の沈黙の後、その頭を折れた扇で叩いてやった手に、不自然に汗が滲んでいたのは暑苦しかったせいだと自分に言い聞かせた。
畳む
#LCB61 #技術解放連合 #K社
雨の檻から連れ出して/ホンイサ
囚人と囚人
しとど降り注ぐ雨に紛れるよう、見慣れた人影があった。露に湿ったところで、うねることなく一層の艶を放つ夜色の豊かな髪。曇天を見つめたまま、まるで精緻な彫刻のごとく、ぴたりとも動かない彼の表情は見えなかったけれど。
「……イサンさん?」
泥濘を踏み締めた足音で、自分以外の存在に気付いたのだろう――はたまた、彼のことだからそれよりも先に己の気配に勘付いてたとして何ら不思議に思わなかった。
「ふふっ、凄い雨ですね~。外に出てまだそれほど経ってないのに、もうびしょ濡れになっちゃいました」
まるで何気ない言葉を口にでもしながら、流れるような所作で振り返った彼の整った白皙は常と変わらぬ笑みを湛えていたけれど、心なしか蒼白を帯びた口唇を視界に捉える。
「……ホンル君。そろそろバスに戻らん」
手の施しようのない致命傷を負ったところで、不治の大病を患ったところで、管理人の時計が巻き戻りさえすれば全てがなかったように肉体は正常を取り戻し、何事もなかったように再び時が巡り出す。
とはいえ、不要な苦痛を友たる彼にかけるべきではない。
――風病に蝕まれ、苦しむ目の前の彼とて、見たいものではない。
「ふふっ、すみません」彼は、変わらず目を細めていた。「時々、ふと雨に打たれたくなる時があるんです。耳を打つ雨音が、肌を叩く雨が、どうしようもなく心地好くて……」
ふいと空を仰いだ眼差しは、遠い。
酷く不安定で、曖昧としていて。
「……」
「イサンさん? どうし――わっ」
泥濘む土を一歩、一歩と近付く自分へと傾げられた頭を、自身の外套で覆い隠した。
「えっ、……え、あの、これ……」
想定の範疇から逸脱していたからだろう。ワンオクターブ上がった声色からは、隠しきれぬ動揺が滲んでいた。外套を掴もうとした手を、離さぬようしっかと搦めとる。
「……あの」
「泥濘に足を取らるまじく、心留めたまえ」
外套によって隠された顔を、決して見ぬようにして。
発せられる音は、一層激しさを増す雨によって掻き消されるままにして。
そうして、バスに向けて一歩を踏み出した。
畳む
#LCB61
囚人と囚人
しとど降り注ぐ雨に紛れるよう、見慣れた人影があった。露に湿ったところで、うねることなく一層の艶を放つ夜色の豊かな髪。曇天を見つめたまま、まるで精緻な彫刻のごとく、ぴたりとも動かない彼の表情は見えなかったけれど。
「……イサンさん?」
泥濘を踏み締めた足音で、自分以外の存在に気付いたのだろう――はたまた、彼のことだからそれよりも先に己の気配に勘付いてたとして何ら不思議に思わなかった。
「ふふっ、凄い雨ですね~。外に出てまだそれほど経ってないのに、もうびしょ濡れになっちゃいました」
まるで何気ない言葉を口にでもしながら、流れるような所作で振り返った彼の整った白皙は常と変わらぬ笑みを湛えていたけれど、心なしか蒼白を帯びた口唇を視界に捉える。
「……ホンル君。そろそろバスに戻らん」
手の施しようのない致命傷を負ったところで、不治の大病を患ったところで、管理人の時計が巻き戻りさえすれば全てがなかったように肉体は正常を取り戻し、何事もなかったように再び時が巡り出す。
とはいえ、不要な苦痛を友たる彼にかけるべきではない。
――風病に蝕まれ、苦しむ目の前の彼とて、見たいものではない。
「ふふっ、すみません」彼は、変わらず目を細めていた。「時々、ふと雨に打たれたくなる時があるんです。耳を打つ雨音が、肌を叩く雨が、どうしようもなく心地好くて……」
ふいと空を仰いだ眼差しは、遠い。
酷く不安定で、曖昧としていて。
「……」
「イサンさん? どうし――わっ」
泥濘む土を一歩、一歩と近付く自分へと傾げられた頭を、自身の外套で覆い隠した。
「えっ、……え、あの、これ……」
想定の範疇から逸脱していたからだろう。ワンオクターブ上がった声色からは、隠しきれぬ動揺が滲んでいた。外套を掴もうとした手を、離さぬようしっかと搦めとる。
「……あの」
「泥濘に足を取らるまじく、心留めたまえ」
外套によって隠された顔を、決して見ぬようにして。
発せられる音は、一層激しさを増す雨によって掻き消されるままにして。
そうして、バスに向けて一歩を踏み出した。
畳む
#LCB61
透明な傷をなぞって/ホンイサ
囚人と囚人
硝子窓から降り注ぐ陽光は目を焼くには柔らかく、心地の好いぬくもりが皮膚に滲みいっていくようだった。朝寝に耽るにはこの上ない気候だというのに、今日は不思議と目が冴えていて、夜着から制服に着替えては、誰よりも一足早く廊下へと足を踏み出す。一つ扉をくぐると、目を焼くような鮮やかな深紅の内装。もはやすっかり馴染みのある光景となったバス構内を染める仄青い陽射しに目を細めながら、ふと視線の先に認めた人影まで歩を進める。自身の座席よりも一歩、前。二人掛けの座席――得物を抱きかかえたまま、自身の指定席に腰かける友を見下ろす。朝の挨拶をしようと開きかけた口は、白皙に影を落とす長い睫毛に慌てて噤んだ。
――眠っている、のだろうか。
不躾な行為だと百も承知で、抗えぬ好奇心のままに覗き込む。あえかに上下する胸元と、ほとんど空気を震わせぬ呼吸。時折うと、うと、と船を漕ぐ顔は普段と比べても、幾分かあどけない。
相当、昨日の業務で疲れが溜まっていたのだろうか。
それとも――薄明の持つ魔力が彼をこうさせたのだろうか。
幸い、自分達以外には誰もいない。管理人や他の囚人がここに来るまでには、もう暫くの猶予が残されているはずだ。未だ夜気の残るバスの空気に体を冷やしてしまわぬよう、身に付けていた外套を、夢の中にある友の肩へと掛けようとした――色彩の異なる双眸が開かれたのは、それとほぼ同時。
瞬きすら許されぬほど、ほんの刹那の出来事だった。骨が軋む力で肩が押され、世界が反転する。強かに打ちつけられた身体の痛みとか、首筋に走った鋭い熱――確実に、急所を狙った斬撃だった。しかし、彼自身によって咄嗟に鋒をずらされた――とか、今ばかりはどうでも良かった。
「……っ、」
それよりも、何よりも。
誰よりも朗らかに笑う整い過ぎた美貌を酷く強ばらせて。
誰よりも美しい宝珠のような瞳を酷く揺らして。
己を見下ろす彼の痛々しさに、心を囚われていた。
「イサン、さん……僕……」
「……ゆっくり、息を吸いたまえ」
――だから、今の私に出来るのは。
震える嗚咽ばかりを零す、呼吸の仕方を忘れた彼を、やおら抱き締めてやることだけだ。
畳む
#LCB61
囚人と囚人
硝子窓から降り注ぐ陽光は目を焼くには柔らかく、心地の好いぬくもりが皮膚に滲みいっていくようだった。朝寝に耽るにはこの上ない気候だというのに、今日は不思議と目が冴えていて、夜着から制服に着替えては、誰よりも一足早く廊下へと足を踏み出す。一つ扉をくぐると、目を焼くような鮮やかな深紅の内装。もはやすっかり馴染みのある光景となったバス構内を染める仄青い陽射しに目を細めながら、ふと視線の先に認めた人影まで歩を進める。自身の座席よりも一歩、前。二人掛けの座席――得物を抱きかかえたまま、自身の指定席に腰かける友を見下ろす。朝の挨拶をしようと開きかけた口は、白皙に影を落とす長い睫毛に慌てて噤んだ。
――眠っている、のだろうか。
不躾な行為だと百も承知で、抗えぬ好奇心のままに覗き込む。あえかに上下する胸元と、ほとんど空気を震わせぬ呼吸。時折うと、うと、と船を漕ぐ顔は普段と比べても、幾分かあどけない。
相当、昨日の業務で疲れが溜まっていたのだろうか。
それとも――薄明の持つ魔力が彼をこうさせたのだろうか。
幸い、自分達以外には誰もいない。管理人や他の囚人がここに来るまでには、もう暫くの猶予が残されているはずだ。未だ夜気の残るバスの空気に体を冷やしてしまわぬよう、身に付けていた外套を、夢の中にある友の肩へと掛けようとした――色彩の異なる双眸が開かれたのは、それとほぼ同時。
瞬きすら許されぬほど、ほんの刹那の出来事だった。骨が軋む力で肩が押され、世界が反転する。強かに打ちつけられた身体の痛みとか、首筋に走った鋭い熱――確実に、急所を狙った斬撃だった。しかし、彼自身によって咄嗟に鋒をずらされた――とか、今ばかりはどうでも良かった。
「……っ、」
それよりも、何よりも。
誰よりも朗らかに笑う整い過ぎた美貌を酷く強ばらせて。
誰よりも美しい宝珠のような瞳を酷く揺らして。
己を見下ろす彼の痛々しさに、心を囚われていた。
「イサン、さん……僕……」
「……ゆっくり、息を吸いたまえ」
――だから、今の私に出来るのは。
震える嗚咽ばかりを零す、呼吸の仕方を忘れた彼を、やおら抱き締めてやることだけだ。
畳む
#LCB61
つたない二人のつくりかた/ホンイサ
囚人と囚人
二人きりの逢瀬、向かい合う薄い唇に触れると、ふるりと震える艶やかな睫毛。次いで、あえかな熱が灯りゆく白皙の頬が眼前に映り込む。イサンと「相思相愛」の関係になってから幾許かの時が経つが、肝心の彼はというと、未だに口吸いという行為に慣れる気配はない――とはいえ、細りとした身を硬直させるばかりだった以前までとは違い、おずおずながらも彼からすすんで唇を寄せてくれるようになった。背に回した腕へと力を籠め、耳まで鮮やかな朱に染めながら離さぬとばかりに己を掻き抱いた彼のいじらしさに、愛おしさばかりが膨れ上がっていったあの瞬間を今でも覚えている。
イサンから求められている――愛されている。もはや疑いようのない確信に至ったからこそ、踏み越えるべきでないラインを見誤ったのかも知れない。僅かに開かれた口唇の隙間から舌を滑り込ませようとして――大袈裟に跳ねた肩。自身のものとは異なるぬくもりに対して、相当気が動転したのだろう。
舌先に触れた硬質な物質が、ぷつりと音を立てて薄い皮膚を食い破る。灼熱めいた痛みを訴える傷口から止め処なく広がる鉄の味に、真っ先に反応したのはイサンだった。
「す、すまない……私は、そなたに怪我を……」
先ほどまで果実のように熟れた色を晒していたはずの顔がたちまち痛々しいほど青褪めていく。先ほどまで甘く蕩けていたはずの双眸が動揺によって酷く揺らいでいた。
「うん? ……あ~」
無論、決して痛みがないわけではない。しかし、過去の鍛錬や日頃の血腥い業務を思えば、この程度の傷であれば問題なく無視出来る。だからこそ、軽い調子で「大丈夫ですよ~」といつも通りの笑顔を浮かべさえするだけで、強張ってしまったその顔を綻ばせてくれるはずだった。
そうであるはずなのに、そうしなかったのは――己の中でどうしようもない悪戯心が芽生えてしまったから。
「そう言われると、確かにちょおっとばかり痛いかも~」
声に出すや否や、一層血の気の引いた白皙に一種の罪悪感を覚えながらも、それを表に出さぬよう目を細め、見せつけるようにして笑みを模る唇を開きながら。
「……ここ、イサンさんが舐めてくれたら、痛みが治るかも知れません」
腫れて赤みを増した舌先を覗かせるようにして、彼に見せつけた。
訪れた沈黙。瞬きを忘れた黒曜石が、まるで人形のように固まったまま、自分を見つめている。彼お得意の思考の海に沈んでいるのか、はたまた思考が停止してしまっているのか。突飛に齎された提案を前にして、彼は最初にどのような表情を見せるだろう。顔を真っ赤にして慌てふためくだろうか。それとも機嫌を損ねてしまうだろうか――覆水盆にかえらずとは言うが、彼に嫌われてしまうのだけは嫌かも知れない。
今ならば、未だ引き返せる。冗談であると告げようとした言葉が、しかし音になることはなかった。
眼前に映り込んだのは、ふるりと震える艶やかな睫毛。次いで、あえかな熱が灯りゆく白皙の頬。
「……ん、」
――そして、薄く開かれた唇から現れた、彼の舌。躊躇いがちに差し出された粘膜が、己の舌先へと刻まれた傷をなぞり、健気にも、懸命に唾液を擦り合わせる様を瞬きも忘れて見入る。
初めて目の当たりにするイサンの舌は想像していた以上に赤かったとか、熱かったとか。
鼓膜に触れる、鼻を抜けるような吐息が酷く扇情的だったとか。
かわいいとか、好きだとか。
とりとめのない感想が、頭に浮かんでは弾け飛んでいく。自分は夢でも見ているのだろうか――けれど、まざまざと感じ取れる生々しいぬくもりこそが、これが夢でないことの証左となった。
誰よりも聡い彼が、何故このような奇行に走ったのか。もはや何かを考えるだけの余裕など、自分にはなかった。
――そしてそれは、きっと彼も同じこと。
畳む
#LCB61
囚人と囚人
二人きりの逢瀬、向かい合う薄い唇に触れると、ふるりと震える艶やかな睫毛。次いで、あえかな熱が灯りゆく白皙の頬が眼前に映り込む。イサンと「相思相愛」の関係になってから幾許かの時が経つが、肝心の彼はというと、未だに口吸いという行為に慣れる気配はない――とはいえ、細りとした身を硬直させるばかりだった以前までとは違い、おずおずながらも彼からすすんで唇を寄せてくれるようになった。背に回した腕へと力を籠め、耳まで鮮やかな朱に染めながら離さぬとばかりに己を掻き抱いた彼のいじらしさに、愛おしさばかりが膨れ上がっていったあの瞬間を今でも覚えている。
イサンから求められている――愛されている。もはや疑いようのない確信に至ったからこそ、踏み越えるべきでないラインを見誤ったのかも知れない。僅かに開かれた口唇の隙間から舌を滑り込ませようとして――大袈裟に跳ねた肩。自身のものとは異なるぬくもりに対して、相当気が動転したのだろう。
舌先に触れた硬質な物質が、ぷつりと音を立てて薄い皮膚を食い破る。灼熱めいた痛みを訴える傷口から止め処なく広がる鉄の味に、真っ先に反応したのはイサンだった。
「す、すまない……私は、そなたに怪我を……」
先ほどまで果実のように熟れた色を晒していたはずの顔がたちまち痛々しいほど青褪めていく。先ほどまで甘く蕩けていたはずの双眸が動揺によって酷く揺らいでいた。
「うん? ……あ~」
無論、決して痛みがないわけではない。しかし、過去の鍛錬や日頃の血腥い業務を思えば、この程度の傷であれば問題なく無視出来る。だからこそ、軽い調子で「大丈夫ですよ~」といつも通りの笑顔を浮かべさえするだけで、強張ってしまったその顔を綻ばせてくれるはずだった。
そうであるはずなのに、そうしなかったのは――己の中でどうしようもない悪戯心が芽生えてしまったから。
「そう言われると、確かにちょおっとばかり痛いかも~」
声に出すや否や、一層血の気の引いた白皙に一種の罪悪感を覚えながらも、それを表に出さぬよう目を細め、見せつけるようにして笑みを模る唇を開きながら。
「……ここ、イサンさんが舐めてくれたら、痛みが治るかも知れません」
腫れて赤みを増した舌先を覗かせるようにして、彼に見せつけた。
訪れた沈黙。瞬きを忘れた黒曜石が、まるで人形のように固まったまま、自分を見つめている。彼お得意の思考の海に沈んでいるのか、はたまた思考が停止してしまっているのか。突飛に齎された提案を前にして、彼は最初にどのような表情を見せるだろう。顔を真っ赤にして慌てふためくだろうか。それとも機嫌を損ねてしまうだろうか――覆水盆にかえらずとは言うが、彼に嫌われてしまうのだけは嫌かも知れない。
今ならば、未だ引き返せる。冗談であると告げようとした言葉が、しかし音になることはなかった。
眼前に映り込んだのは、ふるりと震える艶やかな睫毛。次いで、あえかな熱が灯りゆく白皙の頬。
「……ん、」
――そして、薄く開かれた唇から現れた、彼の舌。躊躇いがちに差し出された粘膜が、己の舌先へと刻まれた傷をなぞり、健気にも、懸命に唾液を擦り合わせる様を瞬きも忘れて見入る。
初めて目の当たりにするイサンの舌は想像していた以上に赤かったとか、熱かったとか。
鼓膜に触れる、鼻を抜けるような吐息が酷く扇情的だったとか。
かわいいとか、好きだとか。
とりとめのない感想が、頭に浮かんでは弾け飛んでいく。自分は夢でも見ているのだろうか――けれど、まざまざと感じ取れる生々しいぬくもりこそが、これが夢でないことの証左となった。
誰よりも聡い彼が、何故このような奇行に走ったのか。もはや何かを考えるだけの余裕など、自分にはなかった。
――そしてそれは、きっと彼も同じこと。
畳む
#LCB61
涙は希釈された祈りであること/ホンイサ
囚人と囚人
どうして僕に、このE.G.Oが抽出されたんでしょうね。
もはや慟哭と呼んで差し支えない――常であれば軽やかな音律を乗せるように、玉を転がすかの如き笑声を紡ぎ出す声帯から発せられているとは到底思えないあれは、本当に己の知る「彼」の声なのだろうか――耳を劈くような悲鳴を上げ、爆ぜて散り散りになり果てた蒼黒の肉塊を視界に映す。
酷く、酷く陰鬱な心地だった。心の柔らかな部分を真綿で包むようにしてぎりぎりと締めあげられるような、名状し難い窒息感。つい先刻、突として落とされた彼の問いかけは、未だに頭の中で反響し続けている。
青い涙を流して泣くばかりの幻想体が一体何を考え、そのような行動を取ったのか。その真意までを推し量ることは出来ても、それが必ずしも正解であるとは限らない。しかし、精神の悉くを擦り減らし、発狂へと至らしめるその響きを――それでも否が応でも泣き止ませる行為に対して、僅かばかりの罪悪感を抱いてしまった事実をただの気の迷いであると、自分には断定出来なかった。
――もしやすると。
かの幻想体は自身の感情に、自我に感化させることによって、彼の気が済むまで「泣ききらせよう」としているのではないか。
突飛な思考が脳裏を過るも、不思議と溜飲の下がるような心地だった。
ホンルという囚人が、自身の感情を発露させることはほとんどない。常に笑顔で、朗らかで、何も考えていないようでいて、他者を慮る言葉を欠かさない青年――そんな彼が時折、ふとした瞬間に酷く達観とした表情を覗かせることがあった。
どこか諦観にも似たような、神妙なそれを目の当たりにするたび、その作り物めいた美しい笑顔の下にはどれほどの感情をひた隠しにしているのかと思索を巡らせることがある。木漏れ日のように優しい微笑が自分に向けられるたび、ふつふつと込み上げる多幸感に顔が綻ぶと同時に、この笑顔がただの作り物でないことを心から願った。
果たしてどれほどの言葉を尽くせば、本当の彼を見つけられるのだろう。
いくら伸ばせど、この手は未だ届かぬというのに。蛙は彼のために滂沱の涙を流してやれる事実に。
不意に、狡いと思ってしまった。
――最も狡いのは、この胸に息衝く醜い感情だというのに。
「イサンさん」
名前を呼ばれた気がして、おもむろに顔を上げる。ちょうど時計が巻き戻り終えたらしい。先程E.G.Oに侵食されたばかりとは思えぬあっけらかんとした面持ちで、彩の異なる珠のような眼差しを己に向けて、彼はいつものように笑っていた。
「そなた、安穏なりや?」
「ふふっ、体が吹き飛ぶくらい、今更なんともないですよ~」
何とはなしに紡がれた言葉。気の抜けた笑顔。
いつも通りの、緊張感のない見慣れた姿。
――そは、真なりや?
「……さりか」
口をついて出かけた疑問が音を成す前に、あえかな苦笑で隠した。
「しかし、精神に並々ならぬ負荷を受けた身なれば、さほどな無理しそ」
「はい。それよりも~……」つ、と眦を撫ぜる心地好いぬくもりにほっとするにも、それはあまりに唐突だった。「イサンさん。目元が赤いですけど、大丈夫ですか~?」
それが彼の指先であると気付くよりも先に、すぐ側にまで迫った端正すぎる顔を、瞬きも忘れて見つめる。
「何を……、」
「う~ん……目も少し潤んじゃってるし、もしかして泣いてました?」
「…………は?」
しばらく、彼から齎された言葉の意味が理解出来なかった。泣いていた? 自分が?
この戦闘中、一遍たりとも涙を流した記憶など自分にはなかった。しかし、気遣わしげに此方を窺う瞳に、明らかな嘘が紛れているようにも見えなくて余計に訳が分からなくなってしまう。おかげで頭の中は顔料で塗り潰したように真っ白だ。
仮に彼の言うことが事実ならば、自分はいつから目を潤ませていたのだろう。
「あはぁ……その調子だと、イサンさん自身も気付いてなかったんですね~」
目の前でころころと笑う彼の声に、現実に引き戻される。珠の双眸は楽しげに細められていたけれど。
「あ~あ。あなたが、僕のために泣いてくれたのなら良かったのに」
気のせいだろうか。微笑を湛えたままの口唇から独り言ちた言葉が、一等柔らかくて優しい響きを帯びていたのは。
畳む
#LCB61
囚人と囚人
どうして僕に、このE.G.Oが抽出されたんでしょうね。
もはや慟哭と呼んで差し支えない――常であれば軽やかな音律を乗せるように、玉を転がすかの如き笑声を紡ぎ出す声帯から発せられているとは到底思えないあれは、本当に己の知る「彼」の声なのだろうか――耳を劈くような悲鳴を上げ、爆ぜて散り散りになり果てた蒼黒の肉塊を視界に映す。
酷く、酷く陰鬱な心地だった。心の柔らかな部分を真綿で包むようにしてぎりぎりと締めあげられるような、名状し難い窒息感。つい先刻、突として落とされた彼の問いかけは、未だに頭の中で反響し続けている。
青い涙を流して泣くばかりの幻想体が一体何を考え、そのような行動を取ったのか。その真意までを推し量ることは出来ても、それが必ずしも正解であるとは限らない。しかし、精神の悉くを擦り減らし、発狂へと至らしめるその響きを――それでも否が応でも泣き止ませる行為に対して、僅かばかりの罪悪感を抱いてしまった事実をただの気の迷いであると、自分には断定出来なかった。
――もしやすると。
かの幻想体は自身の感情に、自我に感化させることによって、彼の気が済むまで「泣ききらせよう」としているのではないか。
突飛な思考が脳裏を過るも、不思議と溜飲の下がるような心地だった。
ホンルという囚人が、自身の感情を発露させることはほとんどない。常に笑顔で、朗らかで、何も考えていないようでいて、他者を慮る言葉を欠かさない青年――そんな彼が時折、ふとした瞬間に酷く達観とした表情を覗かせることがあった。
どこか諦観にも似たような、神妙なそれを目の当たりにするたび、その作り物めいた美しい笑顔の下にはどれほどの感情をひた隠しにしているのかと思索を巡らせることがある。木漏れ日のように優しい微笑が自分に向けられるたび、ふつふつと込み上げる多幸感に顔が綻ぶと同時に、この笑顔がただの作り物でないことを心から願った。
果たしてどれほどの言葉を尽くせば、本当の彼を見つけられるのだろう。
いくら伸ばせど、この手は未だ届かぬというのに。蛙は彼のために滂沱の涙を流してやれる事実に。
不意に、狡いと思ってしまった。
――最も狡いのは、この胸に息衝く醜い感情だというのに。
「イサンさん」
名前を呼ばれた気がして、おもむろに顔を上げる。ちょうど時計が巻き戻り終えたらしい。先程E.G.Oに侵食されたばかりとは思えぬあっけらかんとした面持ちで、彩の異なる珠のような眼差しを己に向けて、彼はいつものように笑っていた。
「そなた、安穏なりや?」
「ふふっ、体が吹き飛ぶくらい、今更なんともないですよ~」
何とはなしに紡がれた言葉。気の抜けた笑顔。
いつも通りの、緊張感のない見慣れた姿。
――そは、真なりや?
「……さりか」
口をついて出かけた疑問が音を成す前に、あえかな苦笑で隠した。
「しかし、精神に並々ならぬ負荷を受けた身なれば、さほどな無理しそ」
「はい。それよりも~……」つ、と眦を撫ぜる心地好いぬくもりにほっとするにも、それはあまりに唐突だった。「イサンさん。目元が赤いですけど、大丈夫ですか~?」
それが彼の指先であると気付くよりも先に、すぐ側にまで迫った端正すぎる顔を、瞬きも忘れて見つめる。
「何を……、」
「う~ん……目も少し潤んじゃってるし、もしかして泣いてました?」
「…………は?」
しばらく、彼から齎された言葉の意味が理解出来なかった。泣いていた? 自分が?
この戦闘中、一遍たりとも涙を流した記憶など自分にはなかった。しかし、気遣わしげに此方を窺う瞳に、明らかな嘘が紛れているようにも見えなくて余計に訳が分からなくなってしまう。おかげで頭の中は顔料で塗り潰したように真っ白だ。
仮に彼の言うことが事実ならば、自分はいつから目を潤ませていたのだろう。
「あはぁ……その調子だと、イサンさん自身も気付いてなかったんですね~」
目の前でころころと笑う彼の声に、現実に引き戻される。珠の双眸は楽しげに細められていたけれど。
「あ~あ。あなたが、僕のために泣いてくれたのなら良かったのに」
気のせいだろうか。微笑を湛えたままの口唇から独り言ちた言葉が、一等柔らかくて優しい響きを帯びていたのは。
畳む
#LCB61
Forget-me-not/ホンイサ ※R-18
ディエーチ協会
ディエーチ協会
残香/ホンイサ
K社と壇香梅
これは、一体どのような状況なのだろうか。
「隣、良いですか?」
そう言って、今まさに――己の返答すら待つ素振りも見せず――隣の座席に腰掛けようとしている男が纏っているボディースーツを、忘れるはずがない。多くの同胞を殺め、数多の血を吸い上げてなお、忌々しいエメラルド色の輝きを損なうことのないそれは、K社に属する三級摘出職職員の装いだった。
男は人懐こい快活な――「摘出」などと称する殺し合いの時と何ら変わらぬ笑みを湛えたまま、異なる彩りを持つ双眸が覗き込んできたかと思いきや。
「あははっ、そんなに睨まないでくださいよ~」まるで鈴でも転がすような声で呑気に笑い、続ける。「今は共闘関係にあるわけですし、わざわざ敵対する必要なんてないじゃないですか」
「戯言を……」
「まあまあそう言わずに~」
笑顔を崩さぬ男の言い分とて、決して間違えているわけではない。今の我々はリンバスカンパニー――その一部署で、管理人を務めるダンテの指示を受けて動く身に過ぎない。仮に周囲の制止を振り切ってでも目の前にいる男と「死闘」を繰り広げ、いずれかの時間が止まったところで、管理人が時針を巻き戻してしまえば、まるで何事もなかったかのように息を吹き返して再び正常に時を刻み始めるのだろう。
これまでの犠牲に一矢を報いることさえ出来ない、何の意味もない、不毛な行為。
それゆえの、不干渉。
「それに僕、前々からあなたとは話してみたいと思ってたんです」
その花枝、身体から直接生えてるんですか?
花で隠れている目はちゃんと見えてるんですか?
花が萎れたり枯れたりすることはあるんですか?
普段はどんな食事をしてるんですか?
――等々。ああ、いつになったらそのお喋りな舌が乾ききって、唖のように黙ってくれるのか。やはり舌の一つくらい切り落としておくべきだったか。若干の後悔に苛まれながらも、矢継ぎ早に投げかけられる彼の問いに対しては溜息で応えを返しながら、視線を向けた盆上に用意されていたのは、なだらかなフォルムを描く白磁の茶壷と茶杯が二つ。他の囚人の影響か、どうやらこの世界線の「イサン」は、最近好んで茶を口にしているらしい――状況からの憶測になるが、何者かをもてなそうと茶を淹れてから間もなくして招集がかかったようだ。
時が過ぎ、すっかり冷めきってしまった茶杯の片割れを持ち上げる。眼前で揺らぐ淡黄色の水面。鼻を近付けてみると、甘やかな花の香りがした。
「それ、もしかして菊花茶です?」
「……そなた、分かるや?」
「あなたの纏う香りの方が強いので、少し自信がなかったんですけどね~。多分そうだと思います……あ、やっぱりそうだ」
同じようにして茶杯を手に取り、香りを楽しみながら――正答に安堵したのか、見目麗しく咲き誇る百花もかくやとばかりの鮮やかな微笑を深める男は、頼んでもいないのに淀みない口調でさらに言葉を紡ぎあげていく。
「懐かしいなぁ。これでも僕、昔はゆったりとお茶をして過ごしてたんですよ~。色んな茶葉を集めて、嗜んできたので、お茶には多少自信があるんです」
「……斯様なやんごとなき趣味を持ちしそなたが、何故K社の摘出職なぞにつきけりや?」
「ふふ、やっと僕に興味を持ってくれました?」
口を衝いて出た疑問に、翡翠めいた瞳が一層の煌きをもって瞬いた。失言だったと舌を打ったところでもう遅い。
しかし、塵ほども興味がないかと問われたならば、それはそれで嘘になる。
口ぶりからも、彼が明らかな嘘を吐いているようには見えない。何より、ほんの僅かな交流でも分かる美しい所作、整った身なりからも鑑みるに、元は相当裕福な家の出だったのだろうと想像に難くなかった。
安穏としたひとときを好んでいたであろうこの男が、どのような経緯を経てK社に入社し、自らの身を血で染め上げるに至ったのか。
――けれど、同時に知ってはならないと頭のどこかで警鐘が鳴り響いている。
視線を、話題を一方的に打ち切るべく、些か大仰な所作で扇子を開いた途端に鼻孔へと広がるえ辛い花の香。僅かに覚えた頭痛を誤魔化すようにして、杯に注がれた茶を一息に呷った。
「……話は終わりき。その茶を飲まば疾く私の前より失せたまえ」
幸い「イサン」が淹れた茶だ。毒の類いが入っているはずもない。それでも、いくら待てども彼は水面を見下ろすばかりで、一向に口をつけようとはしなかった。
「う~ん……お茶のお誘いは嬉しいんですけど~……」しばらくして、心なしか名残惜しげに手の中にあった杯を卓上に戻しながら、男は笑う。「人らしい食事を摂らなくなってから久しくて。もしかすると吐いちゃうかも知れないので、遠慮しておきます」
こともなげに吐露された言葉の意味を、噛み砕くまでにはしばしの時間を要した。
そうして、茶杯を見つめていたはずの眼差しがこちらを捉えたかと思えば、彼は何も言わずに、やがて困ったように目を細める。
待ち望んだものとは程遠い、痛いほどの静寂。
唖のように黙り込んでしまったのは、他でもない自分自身だった。
――果たして、自分は一体、どのような顔をしていたのだろうか。
畳む
#LCB61 #技術解放連合 #K社
K社と壇香梅
これは、一体どのような状況なのだろうか。
「隣、良いですか?」
そう言って、今まさに――己の返答すら待つ素振りも見せず――隣の座席に腰掛けようとしている男が纏っているボディースーツを、忘れるはずがない。多くの同胞を殺め、数多の血を吸い上げてなお、忌々しいエメラルド色の輝きを損なうことのないそれは、K社に属する三級摘出職職員の装いだった。
男は人懐こい快活な――「摘出」などと称する殺し合いの時と何ら変わらぬ笑みを湛えたまま、異なる彩りを持つ双眸が覗き込んできたかと思いきや。
「あははっ、そんなに睨まないでくださいよ~」まるで鈴でも転がすような声で呑気に笑い、続ける。「今は共闘関係にあるわけですし、わざわざ敵対する必要なんてないじゃないですか」
「戯言を……」
「まあまあそう言わずに~」
笑顔を崩さぬ男の言い分とて、決して間違えているわけではない。今の我々はリンバスカンパニー――その一部署で、管理人を務めるダンテの指示を受けて動く身に過ぎない。仮に周囲の制止を振り切ってでも目の前にいる男と「死闘」を繰り広げ、いずれかの時間が止まったところで、管理人が時針を巻き戻してしまえば、まるで何事もなかったかのように息を吹き返して再び正常に時を刻み始めるのだろう。
これまでの犠牲に一矢を報いることさえ出来ない、何の意味もない、不毛な行為。
それゆえの、不干渉。
「それに僕、前々からあなたとは話してみたいと思ってたんです」
その花枝、身体から直接生えてるんですか?
花で隠れている目はちゃんと見えてるんですか?
花が萎れたり枯れたりすることはあるんですか?
普段はどんな食事をしてるんですか?
――等々。ああ、いつになったらそのお喋りな舌が乾ききって、唖のように黙ってくれるのか。やはり舌の一つくらい切り落としておくべきだったか。若干の後悔に苛まれながらも、矢継ぎ早に投げかけられる彼の問いに対しては溜息で応えを返しながら、視線を向けた盆上に用意されていたのは、なだらかなフォルムを描く白磁の茶壷と茶杯が二つ。他の囚人の影響か、どうやらこの世界線の「イサン」は、最近好んで茶を口にしているらしい――状況からの憶測になるが、何者かをもてなそうと茶を淹れてから間もなくして招集がかかったようだ。
時が過ぎ、すっかり冷めきってしまった茶杯の片割れを持ち上げる。眼前で揺らぐ淡黄色の水面。鼻を近付けてみると、甘やかな花の香りがした。
「それ、もしかして菊花茶です?」
「……そなた、分かるや?」
「あなたの纏う香りの方が強いので、少し自信がなかったんですけどね~。多分そうだと思います……あ、やっぱりそうだ」
同じようにして茶杯を手に取り、香りを楽しみながら――正答に安堵したのか、見目麗しく咲き誇る百花もかくやとばかりの鮮やかな微笑を深める男は、頼んでもいないのに淀みない口調でさらに言葉を紡ぎあげていく。
「懐かしいなぁ。これでも僕、昔はゆったりとお茶をして過ごしてたんですよ~。色んな茶葉を集めて、嗜んできたので、お茶には多少自信があるんです」
「……斯様なやんごとなき趣味を持ちしそなたが、何故K社の摘出職なぞにつきけりや?」
「ふふ、やっと僕に興味を持ってくれました?」
口を衝いて出た疑問に、翡翠めいた瞳が一層の煌きをもって瞬いた。失言だったと舌を打ったところでもう遅い。
しかし、塵ほども興味がないかと問われたならば、それはそれで嘘になる。
口ぶりからも、彼が明らかな嘘を吐いているようには見えない。何より、ほんの僅かな交流でも分かる美しい所作、整った身なりからも鑑みるに、元は相当裕福な家の出だったのだろうと想像に難くなかった。
安穏としたひとときを好んでいたであろうこの男が、どのような経緯を経てK社に入社し、自らの身を血で染め上げるに至ったのか。
――けれど、同時に知ってはならないと頭のどこかで警鐘が鳴り響いている。
視線を、話題を一方的に打ち切るべく、些か大仰な所作で扇子を開いた途端に鼻孔へと広がるえ辛い花の香。僅かに覚えた頭痛を誤魔化すようにして、杯に注がれた茶を一息に呷った。
「……話は終わりき。その茶を飲まば疾く私の前より失せたまえ」
幸い「イサン」が淹れた茶だ。毒の類いが入っているはずもない。それでも、いくら待てども彼は水面を見下ろすばかりで、一向に口をつけようとはしなかった。
「う~ん……お茶のお誘いは嬉しいんですけど~……」しばらくして、心なしか名残惜しげに手の中にあった杯を卓上に戻しながら、男は笑う。「人らしい食事を摂らなくなってから久しくて。もしかすると吐いちゃうかも知れないので、遠慮しておきます」
こともなげに吐露された言葉の意味を、噛み砕くまでにはしばしの時間を要した。
そうして、茶杯を見つめていたはずの眼差しがこちらを捉えたかと思えば、彼は何も言わずに、やがて困ったように目を細める。
待ち望んだものとは程遠い、痛いほどの静寂。
唖のように黙り込んでしまったのは、他でもない自分自身だった。
――果たして、自分は一体、どのような顔をしていたのだろうか。
畳む
#LCB61 #技術解放連合 #K社
地獄を描く/良ロジャ
リウ協会
彼女の纏う炎は、普段の彼女のように、皆を包み込むような優しく生ぬるいものではない。頬を撫ぜるだけで皮膚を焼き、骨肉を灰燼に帰すような、より鮮烈で、煌々としていて、苛烈なそれ。猛る火の粉を撒き散らす戦場は、まさに彼女の独壇場だ。その中心で、熱風に踊る髪が焦がれることすら気に留めることなく――まあ、どうせ後ほど高い声でキイキイ喚くのだろうけれど――身を躍らせていた。
肺腑を満たした煙を深く吐き出す。ふいと持ち上げた指先、紫煙をくゆらせていた煙草で彼女の輪郭をなぞっていく。決して短くはない時間、まるで眼前の光景を網膜に焼きつけるかのごとく――刹那の瞬きすら、あまりに惜しい。
自ずと口角が歪む。
「――芸術だな」
独り言ちた呟きは、猛火によってかき消されていった。
畳む
#LCB49 #リウ協会
リウ協会
彼女の纏う炎は、普段の彼女のように、皆を包み込むような優しく生ぬるいものではない。頬を撫ぜるだけで皮膚を焼き、骨肉を灰燼に帰すような、より鮮烈で、煌々としていて、苛烈なそれ。猛る火の粉を撒き散らす戦場は、まさに彼女の独壇場だ。その中心で、熱風に踊る髪が焦がれることすら気に留めることなく――まあ、どうせ後ほど高い声でキイキイ喚くのだろうけれど――身を躍らせていた。
肺腑を満たした煙を深く吐き出す。ふいと持ち上げた指先、紫煙をくゆらせていた煙草で彼女の輪郭をなぞっていく。決して短くはない時間、まるで眼前の光景を網膜に焼きつけるかのごとく――刹那の瞬きすら、あまりに惜しい。
自ずと口角が歪む。
「――芸術だな」
独り言ちた呟きは、猛火によってかき消されていった。
畳む
#LCB49 #リウ協会
血風、咲き誇れ/イサファウ
壇香梅と剣契
風に揺れる濡羽色の髪。
陽光に映る白皙。
伏せた目元に深々と刻まれたくま。
知っている男と瓜二つの――当然だ、彼もまた「イサン」なのだから――けれど、知らない男の持つ扇が空を切ると共に、一等鮮烈な黄色が視界を覆い尽くす。まるで演舞でも披露するかの如く、花色と同じそれが振るわれるたび、一層の鮮やかさを増して花々は咲き乱れ、血の臭いすら掩蔽されてしまうほどに、ぴりっとした蘞辛い香りで鼻孔は満たされていった。
噴き上がる赤が黄色にかかっては、花弁のひとひら、またひとひらを染め上げていく。
息を吸うように刀を振り上げ、吐くようにして斬り伏せる。それが「剣契」と呼ばれる集団だ――しかし、いつしか刀を持つ右手を下ろしたまま、やがて晴れた視界に名残惜しささえ覚えながら、自分はその光景にただただ魅入っていた。
――あんな風に、美しい花を咲かせることが出来たならば。
物言わぬ死屍累々。夥しい血河。
訪れた静謐の中、先ほどと同じ場所に佇む男に何かしらの変わった様子もなく――その身を一切の血を浴びることなく、涼しげな面持ちを崩すことなく、扇で自身の顔をあおいでいる。
「そなた……魂抜けきめりかし?」
不意に、心の臓が高鳴る。
扇で口元を隠したまま、こちらへと向けられた眼差しがあった。まるで自ら爛々と煌めくような金色の眼を、自分は知らない。
畳む
#LCB0102 #技術解放連合 #剣契
壇香梅と剣契
風に揺れる濡羽色の髪。
陽光に映る白皙。
伏せた目元に深々と刻まれたくま。
知っている男と瓜二つの――当然だ、彼もまた「イサン」なのだから――けれど、知らない男の持つ扇が空を切ると共に、一等鮮烈な黄色が視界を覆い尽くす。まるで演舞でも披露するかの如く、花色と同じそれが振るわれるたび、一層の鮮やかさを増して花々は咲き乱れ、血の臭いすら掩蔽されてしまうほどに、ぴりっとした蘞辛い香りで鼻孔は満たされていった。
噴き上がる赤が黄色にかかっては、花弁のひとひら、またひとひらを染め上げていく。
息を吸うように刀を振り上げ、吐くようにして斬り伏せる。それが「剣契」と呼ばれる集団だ――しかし、いつしか刀を持つ右手を下ろしたまま、やがて晴れた視界に名残惜しささえ覚えながら、自分はその光景にただただ魅入っていた。
――あんな風に、美しい花を咲かせることが出来たならば。
物言わぬ死屍累々。夥しい血河。
訪れた静謐の中、先ほどと同じ場所に佇む男に何かしらの変わった様子もなく――その身を一切の血を浴びることなく、涼しげな面持ちを崩すことなく、扇で自身の顔をあおいでいる。
「そなた……魂抜けきめりかし?」
不意に、心の臓が高鳴る。
扇で口元を隠したまま、こちらへと向けられた眼差しがあった。まるで自ら爛々と煌めくような金色の眼を、自分は知らない。
畳む
#LCB0102 #技術解放連合 #剣契
Trick or Treat?/イサファウ
囚人と囚人
「トリックオアトリート」
不寝の晩、夜気のように凛と澄み渡った響きをもって、最もこういった行事に興味を示すことはないと思っていた人物から発せられた魔法の呪文に、イサンは読みかけていた本を危うく手から転げ落としそうになりながら、隣で己を見つめる双眸を凝視してしまった。
「……ファウスト嬢?」
「先程、あなたが囚人に菓子を与えている姿を偶然目撃しましたので」
先程――頁を手繰っていた指先を顎に当て、彼女の言葉を租借する。全ての発端は鏡ダンジョン攻略の合間、殺し合いの最中でありながら、比較的自由に動ける時間、憩いの場におけるロジオンの行動だった。
「ねえおちびちゃん達、今日は何の日か覚えてる?」
「今日、ですか? ええっと……確か、今日は一〇月三一日ですね」
「一〇月三一日というとハロウィンでありまするな! 人々が思い思いに仮装し、『トリックオアトリート』と唱えるだけで菓子がもらえるという! あの!」
「ふふっ、ご名答~」
華やぐような、どこか悪戯めいた満面の笑みを湛えたロジオンがポケットより取り出したのは、色とりどりの包装に包まれた飴玉だ。それ等を二つずつ、手を差し出すようなジェスチャーを取る彼女に倣った二人の手のひらへと乗せていく。
「へ、ろ、ロージャさん?」
「ヴェル達には内緒だからね?」
目を輝かせながら手の上に落ちてきた星めいたそれを眺めるドンキホーテの傍ら、目を瞬かせながら顔を上げたシンクレアに――本人はウィンクをしているつもりなのであろう――両目をぎゅっと瞑りながら、艶やかに粧した己の口元に指を添えた。
「へぇ、ハロウィンっていうんですか。下々ではそういう催しがあるんですね~」
そのような一部始終を観察していたホンルにとって、ハロウィンという行事は多少なりとも新鮮に映ったのだろうか。じゃあ僕も、等とまるで先達の行動を真似るようにして差し出された月餅は明らかに一般人では簡単に手が届かぬほど高級品で、慄く二人と私も欲しいと黄色い声を上げる大きな後ろ姿を遠巻きから眺めながら、ふと、自身の纏う外套のポケットへと手を伸ばす。
謙遜ではなく、本当に大したものではかった。糖分補給用にと用意していた一口サイズのチョコだというのに、渡した途端にぱっと綻ぶあどけない面持ちに、ささやかで尊い日常の一幕に、木漏れ日の中にいるかのようなぬくもりがゆるゆると胸に染み入っていく――そう、ちょうど鏡ダンジョン攻略のメンバーとして、彼女はあの場に居合わせていた。
常と変わらぬ、感情を悟らせぬポーカーフェイスで、まさか彼女が自分に菓子を所望してくるとは夢にも思うまい。
「……イサンさん?」
小首を傾げながら、ファウストはこちらを見つめている。さて、どうしたものか。年少者の二人だけではなく、ホンルとロジオンにもチョコを渡してしまった。ポケットを探る指は何も掴めず、ただただ布地に触れるばかりだ。
「ファウストは知っています。菓子をもらえないのなら悪戯して構わないと」
沈黙と視線ばかりが突き刺さる。
「もらえないのでしたら……いたずら以外の選択はありませんが」
「……待ちたまえ。しばし、待ちたまえ」
「ファウストはもう十分待ちました」
どうやら、これ以上猶予を与えるつもりはないらしい。手のひらに汗が滲む。もう片方のポケットへと手を伸ばす――指先に触れる、固いもの。縋るようにして細長い箇所を摘まみ、引き上げたそれはいつぞや手に入れた――少なくとも自ら購入したものではない。囚人の誰かから譲り受けた品だろう――棒付きのキャンディだった。おそらく葡萄味なのだろうその艶やかな飴先を彼女に向けながら、様子を窺う。
「…………」
「…………」
再び訪れる沈黙。
もしや気に入らなかったのだろうか。
「……致し方ありませんね」血の気が引くような心地など露知らず、差し出されたそれを受け取ろうとする彼女は心なしか不服そうに、白皙の頬を膨らませながら。
「頂きましょう」
そう、小さく溜息を吐いたのだった。
「……彼女は、よりよき品を欲したりけむや?」
「う~ん……ファウも大概だけど、イサンさんはもう少し乙女心を学んだ方がいいかもねぇ?」
畳む
#LCB0102
囚人と囚人
「トリックオアトリート」
不寝の晩、夜気のように凛と澄み渡った響きをもって、最もこういった行事に興味を示すことはないと思っていた人物から発せられた魔法の呪文に、イサンは読みかけていた本を危うく手から転げ落としそうになりながら、隣で己を見つめる双眸を凝視してしまった。
「……ファウスト嬢?」
「先程、あなたが囚人に菓子を与えている姿を偶然目撃しましたので」
先程――頁を手繰っていた指先を顎に当て、彼女の言葉を租借する。全ての発端は鏡ダンジョン攻略の合間、殺し合いの最中でありながら、比較的自由に動ける時間、憩いの場におけるロジオンの行動だった。
「ねえおちびちゃん達、今日は何の日か覚えてる?」
「今日、ですか? ええっと……確か、今日は一〇月三一日ですね」
「一〇月三一日というとハロウィンでありまするな! 人々が思い思いに仮装し、『トリックオアトリート』と唱えるだけで菓子がもらえるという! あの!」
「ふふっ、ご名答~」
華やぐような、どこか悪戯めいた満面の笑みを湛えたロジオンがポケットより取り出したのは、色とりどりの包装に包まれた飴玉だ。それ等を二つずつ、手を差し出すようなジェスチャーを取る彼女に倣った二人の手のひらへと乗せていく。
「へ、ろ、ロージャさん?」
「ヴェル達には内緒だからね?」
目を輝かせながら手の上に落ちてきた星めいたそれを眺めるドンキホーテの傍ら、目を瞬かせながら顔を上げたシンクレアに――本人はウィンクをしているつもりなのであろう――両目をぎゅっと瞑りながら、艶やかに粧した己の口元に指を添えた。
「へぇ、ハロウィンっていうんですか。下々ではそういう催しがあるんですね~」
そのような一部始終を観察していたホンルにとって、ハロウィンという行事は多少なりとも新鮮に映ったのだろうか。じゃあ僕も、等とまるで先達の行動を真似るようにして差し出された月餅は明らかに一般人では簡単に手が届かぬほど高級品で、慄く二人と私も欲しいと黄色い声を上げる大きな後ろ姿を遠巻きから眺めながら、ふと、自身の纏う外套のポケットへと手を伸ばす。
謙遜ではなく、本当に大したものではかった。糖分補給用にと用意していた一口サイズのチョコだというのに、渡した途端にぱっと綻ぶあどけない面持ちに、ささやかで尊い日常の一幕に、木漏れ日の中にいるかのようなぬくもりがゆるゆると胸に染み入っていく――そう、ちょうど鏡ダンジョン攻略のメンバーとして、彼女はあの場に居合わせていた。
常と変わらぬ、感情を悟らせぬポーカーフェイスで、まさか彼女が自分に菓子を所望してくるとは夢にも思うまい。
「……イサンさん?」
小首を傾げながら、ファウストはこちらを見つめている。さて、どうしたものか。年少者の二人だけではなく、ホンルとロジオンにもチョコを渡してしまった。ポケットを探る指は何も掴めず、ただただ布地に触れるばかりだ。
「ファウストは知っています。菓子をもらえないのなら悪戯して構わないと」
沈黙と視線ばかりが突き刺さる。
「もらえないのでしたら……いたずら以外の選択はありませんが」
「……待ちたまえ。しばし、待ちたまえ」
「ファウストはもう十分待ちました」
どうやら、これ以上猶予を与えるつもりはないらしい。手のひらに汗が滲む。もう片方のポケットへと手を伸ばす――指先に触れる、固いもの。縋るようにして細長い箇所を摘まみ、引き上げたそれはいつぞや手に入れた――少なくとも自ら購入したものではない。囚人の誰かから譲り受けた品だろう――棒付きのキャンディだった。おそらく葡萄味なのだろうその艶やかな飴先を彼女に向けながら、様子を窺う。
「…………」
「…………」
再び訪れる沈黙。
もしや気に入らなかったのだろうか。
「……致し方ありませんね」血の気が引くような心地など露知らず、差し出されたそれを受け取ろうとする彼女は心なしか不服そうに、白皙の頬を膨らませながら。
「頂きましょう」
そう、小さく溜息を吐いたのだった。
「……彼女は、よりよき品を欲したりけむや?」
「う~ん……ファウも大概だけど、イサンさんはもう少し乙女心を学んだ方がいいかもねぇ?」
畳む
#LCB0102
花になる日まで眠れ/ホンイサ ※R-18
W社整理要員
W社整理要員
名称未設定の感情/ホンイサ
囚人と囚人
「今、何を考えてるんです?」
茫洋と、バスと外界を隔てる硝子窓の先を眺めていた眼差しがおもむろに此方へと向けられる。月のない夜空をそのまま嵌め込んだかのような昏い双眸は、確かに自分の姿だけを映しているはずなのに、どこか遠くを――自分ではない「誰か」を見ているのではないかと錯覚してしまうほど、酷く虚ろだった。
唐突で不躾な問いかけに対して、彼が眉を顰めることも、微笑を湛えることもしない。人よりも幾許か長い沈思黙考を重ね、淡々とした落ち着いた低音に言の葉を乗せる。
「――何も」
ごくごく短い、最低限の応えを紡ぎ終えると、告げるべきことは告げたと言わんばかりに黒い視線は再び虚空へと注がれる。「白紙」と呼ぶには不自然な、まるで紙いっぱいに描いた絵を全て白い塗料で塗り潰してしまったような違和感を覚えるそれだったけれど、前のめりになってまで回答を追求したいと思えるほど、この青年に対して特段の興味や関心があったわけでもない。
「ふぅん……そうですか」
だから、いつものように笑みを浮かべて、回答への謝辞を伝えてからその場を後にした。
イサン。自分と同じく「リンバスカンパニー」に所属する囚人の一人。口数が少なく、感情の起伏に乏しい彼を冷静沈着な才物だと讃える者もいれば、陰気臭い根暗だと捉える者もいるだろう――とはいえ、最終的には「捉えどころのない不思議な人」という結論に帰結するのだが。
時間の大半を思索に暮れ、思考の処理に費やすイサンが一体何を考え、何を思っているのか――奥まで見通せない霧めいたそれに手を伸ばしたところで、虚空を掠めるばかりで確信を掴めた試しは一度たりともなかった。彼について、さして深くを知りたいとすら思っていなかったのだから、至極当然なことだ。
――イサン。今何を考えてるんだ?
――知るらん。……何も。
あの時と変わらない質問。変わらない回答。
それでもあの瞬間、自分――正確には自分の演ずる「ヨンジ兄」に対してなのだろうけれども――に向けられた微笑は、これまでそう短くもない期間、共に業務をこなしてきた中でさえ初めて目の当たりにするほど、酷く穏やかだったことをほんの少し前のことのように鮮明に覚えている。
イサンの自我心道で与えられた自身の「役柄」が、彼の為人を知るきっかけとなったことは言うまでもない。
だからといって、イサンの心情を慮った末に導き出した推量も、彼を放っておけないと――彼のことをもっと知りたいのだと願ったこの望みの全てが、演じた役柄に感化された結果によるものだと思いたくはなかった。
黄金の枝を回収し、K社の巣を後にしてからどれほどの月日が流れたのか、疾うの前に忘れてしまった。気ままな雑談に花を咲かせる囚人達を乗せ、メフィストフェレスは今日も今日とて時折激しくなる振動に揺られながら、今のところ穏やかな旅路を進む。しかし、こうもバスでの移動ばかりを続けていると身体も鈍るし、どうも退屈で仕方がない。管理人であるダンテに進言すれば、今日の鏡ダンジョン攻略に優先して同行させてもらえないだろうか。
そんなことを考えながら手持無沙汰に髪先を弄ぶ傍ら、ふと視線は目の前の座席に腰かけているイサンへと向けていた。また小難しい書物でも読み解いているらしい彼の横顔は表情こそ普段と変わらないように見えて、心なしか眉間が寄っているような――
「イサンさ~ん」
「! ……ああ。そなた、私に何か用向きなりや?」
弾かれたように見開かれた夜色の瞳が此方を捉えるや否や、安堵でもしたかのようにその目元がふわりと綻ぶ様を見つめては、自ずと頬が緩んでしまいそうになる。自我心道での一件以来、どこかふっきれた様子のイサンを観察していると、何を考えているのか読み取ることさえ難渋したポーカーフェイスは、未だ硬いながらも以前と比べて幾分も柔らかくなり、そして豊かになったように思う。
「用ってほどじゃないんですけど~。何かお悩みのようだったので、少し気になったというか」
「う、うむ……」明らかに、歯切れの悪い応えだった。
おそらく、表情が読み取りやすくなったのも要因の一つかも知れない。今、彼が何を考えているのか、推し量るのは存外に難しいことではなかった。
そういえば、そろそろ昼時だったか。
「もしかして……今日の昼食、何を食べようか迷ってる――とか?」
小首を傾げながら問いかけるも、返ってきたのは沈黙だった――が、落ち着きなくあちこちへ目線を泳がせている挙動を見るに、どうやら図星らしい。ああ、だから理由を言い淀んでいたのか。
「かほん。……ホンル君」
一つ、咳払いをするイサンの頬がほのかに上気する。そんな姿が、どことなくあどけなくて、微笑ましい。
「あははっ、……いやぁ~、まさかこんなことで頭を抱えてるだなんて思わなくて~」
みるみるうちに紅潮していく白皙を眺めては、笑いで震える肩をどうにかこうにか押さえ込む。
「そんなに悩むくらいなら、いっそこうしませんか?」
こちらとしても、別に彼を笑い種にするつもりはない――まあ勘付かれたところで、イサンの人柄を鑑みるに誰も彼の悩みを笑い飛ばしはしないと思うが、彼にも彼の面子がある。それゆえ、あたかも内緒話でもするかのように顔を寄せ合いながら、声を潜める。
「イサンさんが食べたいものを教えてください。僕がそれを選んで、二人で分けるなんてどうです?」
「し、しかし……」
「寧ろ僕も何を食べようか迷ってたところですし願ったり叶ったりですよ~。だから、ここは人助けと思って……ね?」
そう言って見つめた彼の双眸に、あの頃の伽藍洞じみた空虚は見出せなかった。
実際、これといって食べたかったメニューがあるわけでもない。それよりも、何よりも――つい先ほどまで過去に思いを馳せていたからだろうか。今日は、他でもないイサンと共に昼食を摂りたいと思ってしまった。単なる口実に過ぎない言葉の真意に察しがついたのか、どこかばつの悪い表情を浮かべるも、やがてイサンはゆっくりと、その口元を緩やかに綻ばせる。
「……では、そなたの言の葉に甘えん」
「ふふ、こちらこそありがとうございます~」
今この時、この胸が抱いている感情にどのような名称を付けるべきなのか、自分にも分からない。
けれど――きっと「あの日」から。彼から向けられる控えめな笑顔が、ホンルは不思議と、この上なく好きだった。
畳む
#LCB61
囚人と囚人
「今、何を考えてるんです?」
茫洋と、バスと外界を隔てる硝子窓の先を眺めていた眼差しがおもむろに此方へと向けられる。月のない夜空をそのまま嵌め込んだかのような昏い双眸は、確かに自分の姿だけを映しているはずなのに、どこか遠くを――自分ではない「誰か」を見ているのではないかと錯覚してしまうほど、酷く虚ろだった。
唐突で不躾な問いかけに対して、彼が眉を顰めることも、微笑を湛えることもしない。人よりも幾許か長い沈思黙考を重ね、淡々とした落ち着いた低音に言の葉を乗せる。
「――何も」
ごくごく短い、最低限の応えを紡ぎ終えると、告げるべきことは告げたと言わんばかりに黒い視線は再び虚空へと注がれる。「白紙」と呼ぶには不自然な、まるで紙いっぱいに描いた絵を全て白い塗料で塗り潰してしまったような違和感を覚えるそれだったけれど、前のめりになってまで回答を追求したいと思えるほど、この青年に対して特段の興味や関心があったわけでもない。
「ふぅん……そうですか」
だから、いつものように笑みを浮かべて、回答への謝辞を伝えてからその場を後にした。
イサン。自分と同じく「リンバスカンパニー」に所属する囚人の一人。口数が少なく、感情の起伏に乏しい彼を冷静沈着な才物だと讃える者もいれば、陰気臭い根暗だと捉える者もいるだろう――とはいえ、最終的には「捉えどころのない不思議な人」という結論に帰結するのだが。
時間の大半を思索に暮れ、思考の処理に費やすイサンが一体何を考え、何を思っているのか――奥まで見通せない霧めいたそれに手を伸ばしたところで、虚空を掠めるばかりで確信を掴めた試しは一度たりともなかった。彼について、さして深くを知りたいとすら思っていなかったのだから、至極当然なことだ。
――イサン。今何を考えてるんだ?
――知るらん。……何も。
あの時と変わらない質問。変わらない回答。
それでもあの瞬間、自分――正確には自分の演ずる「ヨンジ兄」に対してなのだろうけれども――に向けられた微笑は、これまでそう短くもない期間、共に業務をこなしてきた中でさえ初めて目の当たりにするほど、酷く穏やかだったことをほんの少し前のことのように鮮明に覚えている。
イサンの自我心道で与えられた自身の「役柄」が、彼の為人を知るきっかけとなったことは言うまでもない。
だからといって、イサンの心情を慮った末に導き出した推量も、彼を放っておけないと――彼のことをもっと知りたいのだと願ったこの望みの全てが、演じた役柄に感化された結果によるものだと思いたくはなかった。
黄金の枝を回収し、K社の巣を後にしてからどれほどの月日が流れたのか、疾うの前に忘れてしまった。気ままな雑談に花を咲かせる囚人達を乗せ、メフィストフェレスは今日も今日とて時折激しくなる振動に揺られながら、今のところ穏やかな旅路を進む。しかし、こうもバスでの移動ばかりを続けていると身体も鈍るし、どうも退屈で仕方がない。管理人であるダンテに進言すれば、今日の鏡ダンジョン攻略に優先して同行させてもらえないだろうか。
そんなことを考えながら手持無沙汰に髪先を弄ぶ傍ら、ふと視線は目の前の座席に腰かけているイサンへと向けていた。また小難しい書物でも読み解いているらしい彼の横顔は表情こそ普段と変わらないように見えて、心なしか眉間が寄っているような――
「イサンさ~ん」
「! ……ああ。そなた、私に何か用向きなりや?」
弾かれたように見開かれた夜色の瞳が此方を捉えるや否や、安堵でもしたかのようにその目元がふわりと綻ぶ様を見つめては、自ずと頬が緩んでしまいそうになる。自我心道での一件以来、どこかふっきれた様子のイサンを観察していると、何を考えているのか読み取ることさえ難渋したポーカーフェイスは、未だ硬いながらも以前と比べて幾分も柔らかくなり、そして豊かになったように思う。
「用ってほどじゃないんですけど~。何かお悩みのようだったので、少し気になったというか」
「う、うむ……」明らかに、歯切れの悪い応えだった。
おそらく、表情が読み取りやすくなったのも要因の一つかも知れない。今、彼が何を考えているのか、推し量るのは存外に難しいことではなかった。
そういえば、そろそろ昼時だったか。
「もしかして……今日の昼食、何を食べようか迷ってる――とか?」
小首を傾げながら問いかけるも、返ってきたのは沈黙だった――が、落ち着きなくあちこちへ目線を泳がせている挙動を見るに、どうやら図星らしい。ああ、だから理由を言い淀んでいたのか。
「かほん。……ホンル君」
一つ、咳払いをするイサンの頬がほのかに上気する。そんな姿が、どことなくあどけなくて、微笑ましい。
「あははっ、……いやぁ~、まさかこんなことで頭を抱えてるだなんて思わなくて~」
みるみるうちに紅潮していく白皙を眺めては、笑いで震える肩をどうにかこうにか押さえ込む。
「そんなに悩むくらいなら、いっそこうしませんか?」
こちらとしても、別に彼を笑い種にするつもりはない――まあ勘付かれたところで、イサンの人柄を鑑みるに誰も彼の悩みを笑い飛ばしはしないと思うが、彼にも彼の面子がある。それゆえ、あたかも内緒話でもするかのように顔を寄せ合いながら、声を潜める。
「イサンさんが食べたいものを教えてください。僕がそれを選んで、二人で分けるなんてどうです?」
「し、しかし……」
「寧ろ僕も何を食べようか迷ってたところですし願ったり叶ったりですよ~。だから、ここは人助けと思って……ね?」
そう言って見つめた彼の双眸に、あの頃の伽藍洞じみた空虚は見出せなかった。
実際、これといって食べたかったメニューがあるわけでもない。それよりも、何よりも――つい先ほどまで過去に思いを馳せていたからだろうか。今日は、他でもないイサンと共に昼食を摂りたいと思ってしまった。単なる口実に過ぎない言葉の真意に察しがついたのか、どこかばつの悪い表情を浮かべるも、やがてイサンはゆっくりと、その口元を緩やかに綻ばせる。
「……では、そなたの言の葉に甘えん」
「ふふ、こちらこそありがとうございます~」
今この時、この胸が抱いている感情にどのような名称を付けるべきなのか、自分にも分からない。
けれど――きっと「あの日」から。彼から向けられる控えめな笑顔が、ホンルは不思議と、この上なく好きだった。
畳む
#LCB61
綻びる/ホンイサ
W社整理要員 ※「芽吹く」の続き
夕食を共にして以来、イサンの時間が合えば一緒に食事をすることが多くなった。彼自身、決して口数が多い方ではなかったけれど、想像していたよりもずっと相槌を打つのが上手くて、いつの間にか話し足りないと思えるほど会話が弾んでしまっていただなんて、食事をする前の自分は夢にも思わなかったろう。
つい先日にはちょうどかぶった休日を利用して、二人で街に出かけないかと誘ってみた。最初は友人と外を出歩けるような私服を満足に持っていないからと渋っていたけれど、そんなイサンに似合う服を見繕う時間も退屈ではなかったし、がちがちに緊張していた彼の口元が最終的には柔らかく綻んでいく様を拝めただけでもお釣りがきてしまう。
そういえばこの前はイサンから誘われ、初めて彼の社宅にお邪魔させてもらえたのだけれど、その日は生憎徹夜明けだったようで、持ち寄った映画を二人で鑑賞している途中、舟を漕ぎ始めた彼はそのまま肩へと凭れかかるようにして深い眠りに就いてしまった。ちょっとした気配でもすぐに覚醒する人が、こうも無防備な寝顔を晒してくれるとは思ってもいなくて、これほど自分に気を許してくれている事実に満更でもない気持ちではあったものの、当の本人はこの一件を相当気に病んでしまったらしい。たとえこちらが大丈夫だと言ったところで、何かお詫びをさせなければとても納得してもらえそうにない――ゆえにこそ、変なところで頑固な彼の人柄を利用して、新たな食事の約束を取りつけることが出来たのは僥倖と言うべきだろうか。少しだけ奮発して、良いお店を探してしまった。気に入ってもらえると良いのが。
今日こそがその、心待ちにしていた約束の日。
現在行われているのが、自分にとって本日最後の整理業務。今回のシフトには、どうやらイサンと良秀も参加しているらしい――小耳に挟んだ時は、一体どんな危険な業務に放り込まれるのだと内心冷や冷やしたけれど、今のところ滞りなく業務は進んでいる。
鼻歌交じりで床に転がる「乗客」だったはずの肉塊を――暴れた時には無力化して――解体し、分解し、元々それが位置していた座席に並べ直す、単調な作業。いつもであれば退屈で仕方がない整理業務も、その後に待っている楽しみを思えば、さほど苦にはならなかった。入念に片付けをし終えた車両を一望した後、真っ赤に濡れた手をスラックスで拭い、一つ伸びをする。噎せ返るような血の臭いが充満する車両から外に出ると、吐きそうにしている新人を介抱している年長者、昨日見たバラエティ番組について雑談に興じている同僚、等々――ちらほらと戻ってきた整理要員を眺める限りでは、多少の怪我こそありはすれど、他の車両も順調に作業が完了したのだろう。
期待にも似た眼差しで周囲を探ってみるが、どうやら良秀もイサンも、まだワープ列車から戻っていないようだ。担当車両での業務が思いのほか手間取っているのか、はたまた応援に駆り出されているだけか。
込み上げてくる苦いものを何とか飲み下す。
胸に重い澱が沈んでいく感覚。こうした予感は、往々にして的中するものだ。
「――ファウストさん」
「はい」
プラットホームの傍ら、色素の薄い双眸が、手にあるクリップボードからこちらに向けられた――さりげなく覗き込んでみると、挟まれている書類には、現業務に関する仔細が取りまとめられているようだ。
「応援が必要そうな車両ってありますかね~?」
* * *
まだ理性を保っていた乗客達は、パニックを起こしたり、凶暴化したりした乗客を車両の奥へ奥へと押し込めていったのだろう。中にはかなり距離の離れた客室に乗車しているはずの乗客まで含まれているようで、その全てを元の位置に戻すだけでもかなりの重労働になりそうだ。
「……まあ」
溜息を零しながら、キャップを目深にかぶり直す。今はそんなことに頭を悩ませるよりも、目の前にある「面倒事」を処理する方が先決なのだが。
目の前には一様に意識を失った整理要員が数名――手足が変な方向に曲がっている者もいれば、頭から血を流している者もいるが、幸い呼吸はしている。後ほど適切な治療を受けさえすれば、十分に助かるはずだ――さらに顔を上げた先で呻きを上げるのは、天井に頭が届きそうなほどの巨体。脈動する剥き出しの血管と筋肉質に包まれた、赤い怪物。数百、数千の時を過ごすことでこれほどグロテスクな異形になり得るのだと思うと、人間の進化に対して少しばかりの感動さえ覚える。
「、……っと」
耳を劈く咆哮。同時に「乗客」が床を蹴り、距離を詰められた。瞬く間の突進は握り込んだ得物で辛くも受け止めたが、重い。歯を食いしばり、勢いに圧されて吹き飛びそうになる身体を支えるべく足裏でしっかと硬い床を踏み締め、堪える。がちがちと、得物越しに伝わる振動が一層の激しさを増す。重力を一身に受ける足は徐々に痺れ、感覚はほとんどない。このままでは押し返されるのも時間の問題だった。
翼に入社する以前から、たゆまぬ鍛錬を重ねてきた身だ。多少の暴動であれば鎮圧は造作もないと自負しているが、理性の箍が外れた化け物を相手取らなければならないのは、流石に自分一人では手に余る――とはいえ、自ら志願して応援に駆けつけたからには、ここで無様に逃げ果せるわけにもいかないのだが。
それに――「手に余る」のは、飽くまで「一人だけ」で対処しなければならない状況下においての話だ。
眇めた視界に、刹那に映る、一閃の煌き。赤い巨躯にではなく、次元そのものへと走る亀裂――恍惚とするような紫の光が零れ落ちる空間から現れ、装備どころか頬に飛び散る返り血を意に介しもせず、鋭い身のこなしで怪物を裂いたのは、黒い眼差しの男。
身を翻す間もなく眼前に飛び込んできた肢体を抱き留めた反動でとうとう足は頽れ、床に尻餅をついてしまった。
「い……ったた……」
神経を駆け抜けるような痛みに思わず呻きを漏らすも、自身よりも一回り華奢な腰に回したままの腕は離さなかった。
「ホンル君……? そなた、怪我は――」
自分が探し求めていたその人は、自分が来ることなど予想だにしていなかったのかも知れない。丸みを帯び、忙しなく瞬かせながらこちらを見つめる視線が搗ち合う。普段ならばほとんど感情を映さぬ暗鬱とした双眸が幾許かの吃驚と――まっさきに気遣いに類する光を宿して揺れたことを、秘かに自惚れてしまったところで文句は言われまい。
「お尻が痛い以外は何とも~」
「さりか……さならば、良かりき」
安堵の吐息交じりの微笑には、同じく笑顔で返した。
「それよりも、イサンさんの方こそ怪我はしてませんか~?」
車内灯で青々と照らされた白皙の頬を汚す赤い飛沫を、手袋で皮膚を傷付けないように優しく拭ってやる。そうすると――当人が自覚しているのか、無自覚なのかは別として――心なしか気恥ずかしそうでいて、一方で心地好さそうに頬を擦り寄せてくる反応は、まるで愛玩動物のそれだ。
彼が、こんなにかわいい仕草をすることだって、ただ自分だけが知っていれば良い。
一人悦に入る中、重ねられた手の熱。不意打ちに瞠目する視界を占有するのは、不器用でありながら今まで出会った誰よりも柔らかくてあたたかい微笑。その息遣いが感ぜられるほど近々と感じられた彼の顔を、瞬きも忘れて見つめる。拒みはしなかった――否、拒もうとすら思わなかった、といった方が正しいのかも知れない。こういった行為の際は、目を瞑らなければ失礼に当たるだろうか。惚けたように回らぬ頭でぼんやり思考を巡らせる。待ち望んだ感触は一向に訪れず――ぽすり。左肩へとかかった重みに、ようやく我に返った。
「……イサンさん?」
返事はない。そうっと、撓垂れる身体を揺り動かそうとした指先が捉えた、ぬるい滑り。てらてらとした赤に塗り潰された己の手のひらを目の当たりにして、息が出来なくなった。
怪我をしている。
はやく。
早く、てあてをしなければ。
ねえ、はやくおきてよ。
なんで、こんなによんでもおきないのだろう。
――いやだ。
がちがちと戦慄く口唇でどうにか酸素を取り込む。楽観視が出来るような出血量ではないことは明白で、早く治療を施さなければ手遅れになる。今すぐイサンをここから連れ出して――ああ、そうだ。後は気絶している整理要員の回収、整理業務の応援を要請しなければ――止まりかけた思考に、肉体に鞭を打ち、物言わぬイサンに肩を貸すようにして立ち上がって踏み出した一歩は、酷く重かった。まるで重石でも運んでいるような気分だ。そんなことを考えてしまったところで頭を振る。
まだ、約束を果たしていない。
まだ、死んで良いなどと自分は許していない。
無我夢中で、重い身体を引きずるようにして歩く。そして、無我夢中だったからこそ気付くのが遅れてしまっただなんて、我ながら滑稽だった。
「……あ」
――背後で蠢いている、無力化しきれなかった肉塊の存在に。
振りかざされた腕から庇うようにイサンに覆いかぶさる。衝撃はない。それどころか、痛みすら感じない。おそるおそる顔を上げると、動きを止めた肉塊の四肢が美しい断面図を覗かせながら、ごろりと、重圧のある音を立てて転がった。
「……はあ」
不意に立ち込める煙草の匂いが誰のものか、自分は知っている。
「……良秀、さん?」
「ったく。完・無・気……新人教育の際に教わらなかったのか?」
おかげで素晴らしい芸術を自ら引き剥がす羽目になっちまった。不満げに独り言つ口元に紫煙を燻らせ、ひときわ大きく舌打ちした良秀の赫々とした鋭い眼差しがこちらを睨めつける――が。
「うん? そいつは……」
すぐにその視線は腕の中にあるものへと向けられた。
「なんだ、無様にやられでもしたか?」
「わ、分からないんです。ただ、何度呼びかけても起きないし……背中からたくさん、血も出てて……」
「血?」
「早く、早く診てもらわないと――」
ぐるぐると最悪の事態ばかりが脳裏を過る。暴れ回る鼓動が煩わしい。呼吸が上手く出来ない。もし、このまま目を覚まさなかったら――
刹那、強い衝撃。続いて、頬へと走る熱いものに、しばらくしてようやく自分が殴られたのだと悟る。
「少しは落ち着いたか?」
何故殴られたのだろう。何も考えられなくて、唖然と見上げた彼女の顔は、目に見えてうんざりとした様子で再び舌を打った。
「……おい、ひよっこ。よく聞け」煙を吐き出した良秀は続ける。「背中から血が出てると言ったが……こいつの装備にそれらしい破損はあるか?」
「破損……」
彼女の言葉を反芻しながら、慎重にイサンの背に手を回す。
「……あれ?」
隅々まで確認してみたが、傷らしい傷は見当たらなかった。そんなはずはない。だって、こんなに手が真っ赤に濡れるほど、血が流れているはずなのに――
「…………あ」
次元そのものへと走る亀裂。飛び散る返り血を意に介しもせず、出来たばかりの次元の狭間から姿を現したイサン。
頭を掠めた記憶に、思わず声を上げてしまった。
いや、まさかとは思うが。
「これ……もしかして全部、返り血です?」
「そうでなきゃ、こんなだらしない顔して眠ってられないだろうが」
もはや嘆息めいた溜息を零しながら、眉間に眉を寄せる良秀が指し示す先、胸に抱かれたイサンへと視線を落とす。青く照らされてこそいるけれど、顔色は決して悪くない。か細くも規則正しい寝息を立て、あの休日――初めて訪れた彼の社宅で、隣で見守っていた安穏とした寝顔が、そこにはあった。
まさか、単なる取り越し苦労だったとは。これまでの緊張が全て解けたからか、どっと襲い来る疲労感で身体から力が抜けていく。まったく人騒がせだと言いたいところだが、第一騒いだのは自分自身であるため、心の奥底に沈めておく。
しかし、何故イサンは急に眠りに就いたのだろう。いくら新人教育業務の準備に熱を入れ過ぎて徹夜や残業を重ねた後だったとして、こういったことは今までに一度もなかったはずだ。彼の緊張の糸が切れるきっかけは何か――そこまで考えて、思考を止める。これ以上はいけない。これ以上は、きっと自惚れてしまうから。
「良秀さ~ん……悪いんですけど、武器を預かってもらえません? 流石に持ったままイサンさんを抱えるのは難しくて~」
「やらんぞ。何で俺がそんなことを……」
「そこを何とか~。今度何か奢りますから~」
緩みそうになる口元は、いつもの笑みの下にひた隠す。敏い彼女にはすぐに察せられてしまいそうだけれど、一人だけの秘密にしたかったから。
――一旦綻びてしまった感情は、後は花開く瞬間を待つのみ。
畳む
#LCB61 #W社
W社整理要員 ※「芽吹く」の続き
夕食を共にして以来、イサンの時間が合えば一緒に食事をすることが多くなった。彼自身、決して口数が多い方ではなかったけれど、想像していたよりもずっと相槌を打つのが上手くて、いつの間にか話し足りないと思えるほど会話が弾んでしまっていただなんて、食事をする前の自分は夢にも思わなかったろう。
つい先日にはちょうどかぶった休日を利用して、二人で街に出かけないかと誘ってみた。最初は友人と外を出歩けるような私服を満足に持っていないからと渋っていたけれど、そんなイサンに似合う服を見繕う時間も退屈ではなかったし、がちがちに緊張していた彼の口元が最終的には柔らかく綻んでいく様を拝めただけでもお釣りがきてしまう。
そういえばこの前はイサンから誘われ、初めて彼の社宅にお邪魔させてもらえたのだけれど、その日は生憎徹夜明けだったようで、持ち寄った映画を二人で鑑賞している途中、舟を漕ぎ始めた彼はそのまま肩へと凭れかかるようにして深い眠りに就いてしまった。ちょっとした気配でもすぐに覚醒する人が、こうも無防備な寝顔を晒してくれるとは思ってもいなくて、これほど自分に気を許してくれている事実に満更でもない気持ちではあったものの、当の本人はこの一件を相当気に病んでしまったらしい。たとえこちらが大丈夫だと言ったところで、何かお詫びをさせなければとても納得してもらえそうにない――ゆえにこそ、変なところで頑固な彼の人柄を利用して、新たな食事の約束を取りつけることが出来たのは僥倖と言うべきだろうか。少しだけ奮発して、良いお店を探してしまった。気に入ってもらえると良いのが。
今日こそがその、心待ちにしていた約束の日。
現在行われているのが、自分にとって本日最後の整理業務。今回のシフトには、どうやらイサンと良秀も参加しているらしい――小耳に挟んだ時は、一体どんな危険な業務に放り込まれるのだと内心冷や冷やしたけれど、今のところ滞りなく業務は進んでいる。
鼻歌交じりで床に転がる「乗客」だったはずの肉塊を――暴れた時には無力化して――解体し、分解し、元々それが位置していた座席に並べ直す、単調な作業。いつもであれば退屈で仕方がない整理業務も、その後に待っている楽しみを思えば、さほど苦にはならなかった。入念に片付けをし終えた車両を一望した後、真っ赤に濡れた手をスラックスで拭い、一つ伸びをする。噎せ返るような血の臭いが充満する車両から外に出ると、吐きそうにしている新人を介抱している年長者、昨日見たバラエティ番組について雑談に興じている同僚、等々――ちらほらと戻ってきた整理要員を眺める限りでは、多少の怪我こそありはすれど、他の車両も順調に作業が完了したのだろう。
期待にも似た眼差しで周囲を探ってみるが、どうやら良秀もイサンも、まだワープ列車から戻っていないようだ。担当車両での業務が思いのほか手間取っているのか、はたまた応援に駆り出されているだけか。
込み上げてくる苦いものを何とか飲み下す。
胸に重い澱が沈んでいく感覚。こうした予感は、往々にして的中するものだ。
「――ファウストさん」
「はい」
プラットホームの傍ら、色素の薄い双眸が、手にあるクリップボードからこちらに向けられた――さりげなく覗き込んでみると、挟まれている書類には、現業務に関する仔細が取りまとめられているようだ。
「応援が必要そうな車両ってありますかね~?」
* * *
まだ理性を保っていた乗客達は、パニックを起こしたり、凶暴化したりした乗客を車両の奥へ奥へと押し込めていったのだろう。中にはかなり距離の離れた客室に乗車しているはずの乗客まで含まれているようで、その全てを元の位置に戻すだけでもかなりの重労働になりそうだ。
「……まあ」
溜息を零しながら、キャップを目深にかぶり直す。今はそんなことに頭を悩ませるよりも、目の前にある「面倒事」を処理する方が先決なのだが。
目の前には一様に意識を失った整理要員が数名――手足が変な方向に曲がっている者もいれば、頭から血を流している者もいるが、幸い呼吸はしている。後ほど適切な治療を受けさえすれば、十分に助かるはずだ――さらに顔を上げた先で呻きを上げるのは、天井に頭が届きそうなほどの巨体。脈動する剥き出しの血管と筋肉質に包まれた、赤い怪物。数百、数千の時を過ごすことでこれほどグロテスクな異形になり得るのだと思うと、人間の進化に対して少しばかりの感動さえ覚える。
「、……っと」
耳を劈く咆哮。同時に「乗客」が床を蹴り、距離を詰められた。瞬く間の突進は握り込んだ得物で辛くも受け止めたが、重い。歯を食いしばり、勢いに圧されて吹き飛びそうになる身体を支えるべく足裏でしっかと硬い床を踏み締め、堪える。がちがちと、得物越しに伝わる振動が一層の激しさを増す。重力を一身に受ける足は徐々に痺れ、感覚はほとんどない。このままでは押し返されるのも時間の問題だった。
翼に入社する以前から、たゆまぬ鍛錬を重ねてきた身だ。多少の暴動であれば鎮圧は造作もないと自負しているが、理性の箍が外れた化け物を相手取らなければならないのは、流石に自分一人では手に余る――とはいえ、自ら志願して応援に駆けつけたからには、ここで無様に逃げ果せるわけにもいかないのだが。
それに――「手に余る」のは、飽くまで「一人だけ」で対処しなければならない状況下においての話だ。
眇めた視界に、刹那に映る、一閃の煌き。赤い巨躯にではなく、次元そのものへと走る亀裂――恍惚とするような紫の光が零れ落ちる空間から現れ、装備どころか頬に飛び散る返り血を意に介しもせず、鋭い身のこなしで怪物を裂いたのは、黒い眼差しの男。
身を翻す間もなく眼前に飛び込んできた肢体を抱き留めた反動でとうとう足は頽れ、床に尻餅をついてしまった。
「い……ったた……」
神経を駆け抜けるような痛みに思わず呻きを漏らすも、自身よりも一回り華奢な腰に回したままの腕は離さなかった。
「ホンル君……? そなた、怪我は――」
自分が探し求めていたその人は、自分が来ることなど予想だにしていなかったのかも知れない。丸みを帯び、忙しなく瞬かせながらこちらを見つめる視線が搗ち合う。普段ならばほとんど感情を映さぬ暗鬱とした双眸が幾許かの吃驚と――まっさきに気遣いに類する光を宿して揺れたことを、秘かに自惚れてしまったところで文句は言われまい。
「お尻が痛い以外は何とも~」
「さりか……さならば、良かりき」
安堵の吐息交じりの微笑には、同じく笑顔で返した。
「それよりも、イサンさんの方こそ怪我はしてませんか~?」
車内灯で青々と照らされた白皙の頬を汚す赤い飛沫を、手袋で皮膚を傷付けないように優しく拭ってやる。そうすると――当人が自覚しているのか、無自覚なのかは別として――心なしか気恥ずかしそうでいて、一方で心地好さそうに頬を擦り寄せてくる反応は、まるで愛玩動物のそれだ。
彼が、こんなにかわいい仕草をすることだって、ただ自分だけが知っていれば良い。
一人悦に入る中、重ねられた手の熱。不意打ちに瞠目する視界を占有するのは、不器用でありながら今まで出会った誰よりも柔らかくてあたたかい微笑。その息遣いが感ぜられるほど近々と感じられた彼の顔を、瞬きも忘れて見つめる。拒みはしなかった――否、拒もうとすら思わなかった、といった方が正しいのかも知れない。こういった行為の際は、目を瞑らなければ失礼に当たるだろうか。惚けたように回らぬ頭でぼんやり思考を巡らせる。待ち望んだ感触は一向に訪れず――ぽすり。左肩へとかかった重みに、ようやく我に返った。
「……イサンさん?」
返事はない。そうっと、撓垂れる身体を揺り動かそうとした指先が捉えた、ぬるい滑り。てらてらとした赤に塗り潰された己の手のひらを目の当たりにして、息が出来なくなった。
怪我をしている。
はやく。
早く、てあてをしなければ。
ねえ、はやくおきてよ。
なんで、こんなによんでもおきないのだろう。
――いやだ。
がちがちと戦慄く口唇でどうにか酸素を取り込む。楽観視が出来るような出血量ではないことは明白で、早く治療を施さなければ手遅れになる。今すぐイサンをここから連れ出して――ああ、そうだ。後は気絶している整理要員の回収、整理業務の応援を要請しなければ――止まりかけた思考に、肉体に鞭を打ち、物言わぬイサンに肩を貸すようにして立ち上がって踏み出した一歩は、酷く重かった。まるで重石でも運んでいるような気分だ。そんなことを考えてしまったところで頭を振る。
まだ、約束を果たしていない。
まだ、死んで良いなどと自分は許していない。
無我夢中で、重い身体を引きずるようにして歩く。そして、無我夢中だったからこそ気付くのが遅れてしまっただなんて、我ながら滑稽だった。
「……あ」
――背後で蠢いている、無力化しきれなかった肉塊の存在に。
振りかざされた腕から庇うようにイサンに覆いかぶさる。衝撃はない。それどころか、痛みすら感じない。おそるおそる顔を上げると、動きを止めた肉塊の四肢が美しい断面図を覗かせながら、ごろりと、重圧のある音を立てて転がった。
「……はあ」
不意に立ち込める煙草の匂いが誰のものか、自分は知っている。
「……良秀、さん?」
「ったく。完・無・気……新人教育の際に教わらなかったのか?」
おかげで素晴らしい芸術を自ら引き剥がす羽目になっちまった。不満げに独り言つ口元に紫煙を燻らせ、ひときわ大きく舌打ちした良秀の赫々とした鋭い眼差しがこちらを睨めつける――が。
「うん? そいつは……」
すぐにその視線は腕の中にあるものへと向けられた。
「なんだ、無様にやられでもしたか?」
「わ、分からないんです。ただ、何度呼びかけても起きないし……背中からたくさん、血も出てて……」
「血?」
「早く、早く診てもらわないと――」
ぐるぐると最悪の事態ばかりが脳裏を過る。暴れ回る鼓動が煩わしい。呼吸が上手く出来ない。もし、このまま目を覚まさなかったら――
刹那、強い衝撃。続いて、頬へと走る熱いものに、しばらくしてようやく自分が殴られたのだと悟る。
「少しは落ち着いたか?」
何故殴られたのだろう。何も考えられなくて、唖然と見上げた彼女の顔は、目に見えてうんざりとした様子で再び舌を打った。
「……おい、ひよっこ。よく聞け」煙を吐き出した良秀は続ける。「背中から血が出てると言ったが……こいつの装備にそれらしい破損はあるか?」
「破損……」
彼女の言葉を反芻しながら、慎重にイサンの背に手を回す。
「……あれ?」
隅々まで確認してみたが、傷らしい傷は見当たらなかった。そんなはずはない。だって、こんなに手が真っ赤に濡れるほど、血が流れているはずなのに――
「…………あ」
次元そのものへと走る亀裂。飛び散る返り血を意に介しもせず、出来たばかりの次元の狭間から姿を現したイサン。
頭を掠めた記憶に、思わず声を上げてしまった。
いや、まさかとは思うが。
「これ……もしかして全部、返り血です?」
「そうでなきゃ、こんなだらしない顔して眠ってられないだろうが」
もはや嘆息めいた溜息を零しながら、眉間に眉を寄せる良秀が指し示す先、胸に抱かれたイサンへと視線を落とす。青く照らされてこそいるけれど、顔色は決して悪くない。か細くも規則正しい寝息を立て、あの休日――初めて訪れた彼の社宅で、隣で見守っていた安穏とした寝顔が、そこにはあった。
まさか、単なる取り越し苦労だったとは。これまでの緊張が全て解けたからか、どっと襲い来る疲労感で身体から力が抜けていく。まったく人騒がせだと言いたいところだが、第一騒いだのは自分自身であるため、心の奥底に沈めておく。
しかし、何故イサンは急に眠りに就いたのだろう。いくら新人教育業務の準備に熱を入れ過ぎて徹夜や残業を重ねた後だったとして、こういったことは今までに一度もなかったはずだ。彼の緊張の糸が切れるきっかけは何か――そこまで考えて、思考を止める。これ以上はいけない。これ以上は、きっと自惚れてしまうから。
「良秀さ~ん……悪いんですけど、武器を預かってもらえません? 流石に持ったままイサンさんを抱えるのは難しくて~」
「やらんぞ。何で俺がそんなことを……」
「そこを何とか~。今度何か奢りますから~」
緩みそうになる口元は、いつもの笑みの下にひた隠す。敏い彼女にはすぐに察せられてしまいそうだけれど、一人だけの秘密にしたかったから。
――一旦綻びてしまった感情は、後は花開く瞬間を待つのみ。
畳む
#LCB61 #W社
芽吹く/ホンイサ
W社整理要員
イサンという人物がどのような人物なのか問われたところで、彼と接点がないに等しい自分が答えられることは限られている。
たとえば、彼が自分よりも階級の高い三級整理要員であることとか。
新人の頃、彼が新人研修の師範役として教鞭を執っていたこととか。
普段は風に吹かれればそのまま飛んでいきそうなほどぼうっとしているのに、整理業務中の立ち居振る舞いは敏捷で無駄がないこととか。
あとは――W社で勤務し始めてそこそこの時間が経ったが、彼が怒る場面はおろか、微笑む姿すら一度たりとも見たことはなかったように思う。ただただ粛々と業務をこなし、取り乱すことなく冷静に、いや、まるで心をどこかに落としてきたかのような――とはいえ、新人研修の時はどこか楽しげだったかも知れない。人にものを教えるのが好きなのだろうか――能面めいた無表情を崩すことのなかった彼は、存外にも他者に対して寛容らしい。時には整理業務中に負傷した整理要員の代打として、時にはどうしても外せない用事があると頭を下げる社員の代わりとして、夜間及び終電の整理業務に従事する様子をこれまでにそれなりの頻度で見てきた。勿論、彼が加わることで作業効率は飛躍的に向上するので共に仕事をする側としてはありがたい限りだが、その次の日も自分が出勤する頃にはすでに業務の支度をしているイサンの姿を見かけるせいで、はたして彼は人間に必要な睡眠をまともに取れているかどうかすら不思議に思うことがあった――ふとした疑問に対する回答は、目の下に拵えた隈が如実に物語っているだろう。
彼がそこまで身を粉にして働いている理由など、皆目見当もつかない。身近な知人――良秀のように整理業務という天職に喜びを見出しているとは、とてもではないが考えにくい。それならば困った人を見過ごせないというただの純然たる親切心か、はたまた自分の方が仕事を効率的に済ませられるという自信や傲りと言われた方がまだ納得出来る。
第一、自分から接点がないと言いきったはずの男について、何故今更になって、その上柄にもなくああでもないこうでもないと延々と思考と推論を繰り返しているのか。
おそらく、雑談に花を咲かせる同僚達の会話を小耳に挟んでしまったのが原因だ。業務中、「乗客」の暴走によって整理職員数名が全治数週間の負傷を被ったという。しかも件の乗客を取り押さえられず、やむなく三級整理要員が増援に向かったと聞いた。今日は珍しく良秀が上機嫌だったことから、列車整理に宛てがわれたのだと察しはついていたが――なるほど、その内の一人にイサンも含まれていたらしい。
二級から三級への昇格はそう簡単なことではない。無論、彼等が口々に三級整理要員の戦闘能力に対して賞賛の声を贈っていたことは確かだが、中には謂れのない中傷も含まれているものだ。
イサンさんは何を考えているのか分からない――気味が悪い、と。
「……っと、いけないいけない」
これ以上思考を引きずられたところでろくなことはない。本日最後の整理業務はすでに完了した。時計を確認すると、定時まであと少しだ。帰宅する途中で気になっていたレストランにでも立ち寄って、あたたかい夕食で腹を満たせば、多少なりとも思考だってリセット出来るに違いない。ぐっと伸びを一つ、足取り軽く廊下の角を抜けようとした目前で、不意に誰かの話し声が鼓膜を打つ。この先には更衣室があるはずだが、近くで同じく定時を迎えようとしている社員達が話でもしているのだろうか。首をもたげる好奇心の赴くまま、角からこそりと顔を覗かせると、まず視界に入ったのは整理職員と――確か、彼も三級整理要員だったことを覚えている――そして、その手前にイサンの後ろ姿があった。
「今日のトラブルで終電勤務だった整理要員が不足しててな……悪いんだがイサン、代わりに入れないか?」
うわあ、と知らず知らずのうちに声が漏れてしまっていた。よりによって、こんな時に限ってタイミングが悪い。口ぶりからして人手が足りていないのは事実だろうけれど、彼とまたどうせイサンならば断りきれないと踏んで声をかけたのだろう。こんなところにいては、下手をすれば自分まで巻き込まれる形で夜間残業を言い渡されかねない。ここは勘付かれる前に、距離を取って適当に時間を潰した方が良さそうだ。
細心の注意を払いながら踵を返そうとして――ふと、これまでまじまじと見ることのなかったイサンの横顔を一瞥する。普段と変わらない、生気の抜けた無表情。どこか遠くへと向けられているような昏い眼差しから垣間見えた感情は悲観ではなく、かといって達観の境地に達しているわけでもない。
きっとそれは――諦観。
「ちょっとイサンさ~ん!」
手足を動かすよりも先に、気付けば口を開いていた。一歩遅れる形で勢いをつけて背後からのしかかるようにして抱き竦めると、分かりやすいほど吃驚の色に染まった双眸がこちらへ向けられる。
「もぅ、僕との約束のこと忘れちゃったんですか~?」
状況が理解出来ていないのだろう。忙しなく目を白黒させているイサンの耳元で――合わせて――彼にのみ聞こえるように囁きを落とすと、ぱっと人好きのする笑みを顔を貼り付けた。
「すみません~。お手伝いしたいのは山々なんですけど、今日はイサンさんとご飯を食べに行く約束をしてまして~」
そうですよね~、と同意を求めたならば、時が止まったかのように微動だにしなかったイサンが弾かれたように、ぎこちない動きながら首を縦に振る。
「何だお前ら、そんなに仲良かったのか?」
「それはもう~。イサンさん、最近残業続きだったのでたまには美味しいものでも食べて英気を養ってもらおうと思って~」
我ながら、思いつきの即興が次から次へと口を衝いて出るものだと感心する。今日イサンを助けたところで、明日には晴れて、何の接点もない他人同士なのだから。そうなると分かっていながら、どうしてこれほど彼の肩を持とうとしたのか、今更考えたところで明確な理由は浮かんでこない。
いや、もし、あるとするならば――
「何だ、随分楽しそうなことを話しているじゃないか。俺も仲間に入れてくれないか?」
刹那、背中越しに届いた声があった。
「……げっ」
心なしか聞き覚えのある凛としたそれに、目の前に立っている男の表情が露骨なまでに歪んでいく様に目を瞬かせながら、恐る恐ると振り返ってみる。切れ長の赤い双眸を楽しげに細めたその人は、しかし茶番劇に興ずる自分達の存在など気にも留めず、淀みない足取りで職員の前へと歩み寄った。
「ちょうど暇していたところなんだ。人手が足りないって言うなら、夜間だけなんて言わずに今からでも構わないぞ。何、遠慮するな」
普段であればほとんど見せることのない喜色を湛える彼女に詰め寄られる職員の顔色は、もはや蝋のように生気を失ってしまっている。何とかしてこの状況から逃げる術を模索しているのだろう。まるで助けを求めるように視線を泳がせている姿があまりに憐れで、心ともなく同情してしまった。
「あ、ああ悪い用事を思い出した! お前ら、遊ぶのはいいが羽目を外しすぎないように気を付けて帰れよ!」
挙句の果てには脇目も振らずに走り去っていく背中を見送る傍ら。
「ちっ、腰抜けが」
肝心の良秀はといえば、先ほどと打って変わり、自身の不機嫌を隠す気などなく舌を打った。これは――彼女の思惑は別にあるして――彼女に助けられたと考えていいだろう。
「おぉ……流石です、良秀さん。おかげで助かりました~」
満面の笑みを伴い、両手を叩きながら近付く。案の定、鋭い眼光に睨めつけられた。
「何だ、まだいたのか?」
いつものように紫煙を燻らせながら、普段と変わらないぞんざいな彼女の応えに、寧ろ安心感さえ芽生えてくる。
「だって、お礼がまだでしたし~」
「ホンル君の言う通りなり」追随するようにしてイサンはようやく口を開く。「私からも礼を言わせなむ。……二人とも、此度はかたじけなし」
「礼の一つを寄越すくらいなら、一件でも多く俺に整理業務を割り振るよう掛け合ってくれよ」
俺はより多くの芸術と出会いたいだけだからな――煙を吐き出しながら続けられた彼女の言葉は、どこまでも自分自身に正直だった。まあ、そこが彼女らしいと言えばらしいのだが。
「あは、どういたしまして~。それにしても……ん~……気が抜けたら一気に小腹が空いてきちゃいました」伸びの動作に合わせて時計を見上げる。就業時間はとっくに過ぎていた。「折角ですし、このまま何か食べに行きませんか?」
そう言って、覗き込んだイサンの丸みを帯びた瞳にあえかな光が宿る瞬間を見た。まさか、本当に誘われるとは夢にも思っていなかったのだろうか。接してみてようやく気付いたことだが、確かにほとんど表情に変化は見られないとはいえ、彼は存外に驚きやすく、動揺しやすい。
「あ、もしかしてこのまま帰ろうって思ってました? え~……僕、夕食を食べに行こうって約束したじゃないですか~。酷いなあ」
その証拠として、いっそわざとらしく頬を膨らませると、慌てふためくイサンの挙動が面白くて、思わず噴出しそうになるのを何とか堪える。
「あ、あれや演技ならざりける?」
「演技じゃないですよ~。今、演技じゃなくなりました」
子どもの屁理屈だが、このまま別れるには惜しい――もう少しだけ、彼と話してみたいと思ってしまったことは確かだ。
「勿論、良秀さんもご一緒しますよね?」
「おいイサン、断っていいぞ。俺も帰るからな」
「そんな~。僕と良秀さんの仲じゃないですか~」
「気・悪・言。叩き斬るぞ?」
いつも通りの言葉の応酬。ただ、いつもと違うことがあるとすれば。
「…………ふふ、」
その中に、堪えきれずにとうとう零れ落ちた笑声が一つ、混じったことくらい。
――それはきっと、これから何かが芽吹く予兆。
畳む
#LCB61 #W社
W社整理要員
イサンという人物がどのような人物なのか問われたところで、彼と接点がないに等しい自分が答えられることは限られている。
たとえば、彼が自分よりも階級の高い三級整理要員であることとか。
新人の頃、彼が新人研修の師範役として教鞭を執っていたこととか。
普段は風に吹かれればそのまま飛んでいきそうなほどぼうっとしているのに、整理業務中の立ち居振る舞いは敏捷で無駄がないこととか。
あとは――W社で勤務し始めてそこそこの時間が経ったが、彼が怒る場面はおろか、微笑む姿すら一度たりとも見たことはなかったように思う。ただただ粛々と業務をこなし、取り乱すことなく冷静に、いや、まるで心をどこかに落としてきたかのような――とはいえ、新人研修の時はどこか楽しげだったかも知れない。人にものを教えるのが好きなのだろうか――能面めいた無表情を崩すことのなかった彼は、存外にも他者に対して寛容らしい。時には整理業務中に負傷した整理要員の代打として、時にはどうしても外せない用事があると頭を下げる社員の代わりとして、夜間及び終電の整理業務に従事する様子をこれまでにそれなりの頻度で見てきた。勿論、彼が加わることで作業効率は飛躍的に向上するので共に仕事をする側としてはありがたい限りだが、その次の日も自分が出勤する頃にはすでに業務の支度をしているイサンの姿を見かけるせいで、はたして彼は人間に必要な睡眠をまともに取れているかどうかすら不思議に思うことがあった――ふとした疑問に対する回答は、目の下に拵えた隈が如実に物語っているだろう。
彼がそこまで身を粉にして働いている理由など、皆目見当もつかない。身近な知人――良秀のように整理業務という天職に喜びを見出しているとは、とてもではないが考えにくい。それならば困った人を見過ごせないというただの純然たる親切心か、はたまた自分の方が仕事を効率的に済ませられるという自信や傲りと言われた方がまだ納得出来る。
第一、自分から接点がないと言いきったはずの男について、何故今更になって、その上柄にもなくああでもないこうでもないと延々と思考と推論を繰り返しているのか。
おそらく、雑談に花を咲かせる同僚達の会話を小耳に挟んでしまったのが原因だ。業務中、「乗客」の暴走によって整理職員数名が全治数週間の負傷を被ったという。しかも件の乗客を取り押さえられず、やむなく三級整理要員が増援に向かったと聞いた。今日は珍しく良秀が上機嫌だったことから、列車整理に宛てがわれたのだと察しはついていたが――なるほど、その内の一人にイサンも含まれていたらしい。
二級から三級への昇格はそう簡単なことではない。無論、彼等が口々に三級整理要員の戦闘能力に対して賞賛の声を贈っていたことは確かだが、中には謂れのない中傷も含まれているものだ。
イサンさんは何を考えているのか分からない――気味が悪い、と。
「……っと、いけないいけない」
これ以上思考を引きずられたところでろくなことはない。本日最後の整理業務はすでに完了した。時計を確認すると、定時まであと少しだ。帰宅する途中で気になっていたレストランにでも立ち寄って、あたたかい夕食で腹を満たせば、多少なりとも思考だってリセット出来るに違いない。ぐっと伸びを一つ、足取り軽く廊下の角を抜けようとした目前で、不意に誰かの話し声が鼓膜を打つ。この先には更衣室があるはずだが、近くで同じく定時を迎えようとしている社員達が話でもしているのだろうか。首をもたげる好奇心の赴くまま、角からこそりと顔を覗かせると、まず視界に入ったのは整理職員と――確か、彼も三級整理要員だったことを覚えている――そして、その手前にイサンの後ろ姿があった。
「今日のトラブルで終電勤務だった整理要員が不足しててな……悪いんだがイサン、代わりに入れないか?」
うわあ、と知らず知らずのうちに声が漏れてしまっていた。よりによって、こんな時に限ってタイミングが悪い。口ぶりからして人手が足りていないのは事実だろうけれど、彼とまたどうせイサンならば断りきれないと踏んで声をかけたのだろう。こんなところにいては、下手をすれば自分まで巻き込まれる形で夜間残業を言い渡されかねない。ここは勘付かれる前に、距離を取って適当に時間を潰した方が良さそうだ。
細心の注意を払いながら踵を返そうとして――ふと、これまでまじまじと見ることのなかったイサンの横顔を一瞥する。普段と変わらない、生気の抜けた無表情。どこか遠くへと向けられているような昏い眼差しから垣間見えた感情は悲観ではなく、かといって達観の境地に達しているわけでもない。
きっとそれは――諦観。
「ちょっとイサンさ~ん!」
手足を動かすよりも先に、気付けば口を開いていた。一歩遅れる形で勢いをつけて背後からのしかかるようにして抱き竦めると、分かりやすいほど吃驚の色に染まった双眸がこちらへ向けられる。
「もぅ、僕との約束のこと忘れちゃったんですか~?」
状況が理解出来ていないのだろう。忙しなく目を白黒させているイサンの耳元で――合わせて――彼にのみ聞こえるように囁きを落とすと、ぱっと人好きのする笑みを顔を貼り付けた。
「すみません~。お手伝いしたいのは山々なんですけど、今日はイサンさんとご飯を食べに行く約束をしてまして~」
そうですよね~、と同意を求めたならば、時が止まったかのように微動だにしなかったイサンが弾かれたように、ぎこちない動きながら首を縦に振る。
「何だお前ら、そんなに仲良かったのか?」
「それはもう~。イサンさん、最近残業続きだったのでたまには美味しいものでも食べて英気を養ってもらおうと思って~」
我ながら、思いつきの即興が次から次へと口を衝いて出るものだと感心する。今日イサンを助けたところで、明日には晴れて、何の接点もない他人同士なのだから。そうなると分かっていながら、どうしてこれほど彼の肩を持とうとしたのか、今更考えたところで明確な理由は浮かんでこない。
いや、もし、あるとするならば――
「何だ、随分楽しそうなことを話しているじゃないか。俺も仲間に入れてくれないか?」
刹那、背中越しに届いた声があった。
「……げっ」
心なしか聞き覚えのある凛としたそれに、目の前に立っている男の表情が露骨なまでに歪んでいく様に目を瞬かせながら、恐る恐ると振り返ってみる。切れ長の赤い双眸を楽しげに細めたその人は、しかし茶番劇に興ずる自分達の存在など気にも留めず、淀みない足取りで職員の前へと歩み寄った。
「ちょうど暇していたところなんだ。人手が足りないって言うなら、夜間だけなんて言わずに今からでも構わないぞ。何、遠慮するな」
普段であればほとんど見せることのない喜色を湛える彼女に詰め寄られる職員の顔色は、もはや蝋のように生気を失ってしまっている。何とかしてこの状況から逃げる術を模索しているのだろう。まるで助けを求めるように視線を泳がせている姿があまりに憐れで、心ともなく同情してしまった。
「あ、ああ悪い用事を思い出した! お前ら、遊ぶのはいいが羽目を外しすぎないように気を付けて帰れよ!」
挙句の果てには脇目も振らずに走り去っていく背中を見送る傍ら。
「ちっ、腰抜けが」
肝心の良秀はといえば、先ほどと打って変わり、自身の不機嫌を隠す気などなく舌を打った。これは――彼女の思惑は別にあるして――彼女に助けられたと考えていいだろう。
「おぉ……流石です、良秀さん。おかげで助かりました~」
満面の笑みを伴い、両手を叩きながら近付く。案の定、鋭い眼光に睨めつけられた。
「何だ、まだいたのか?」
いつものように紫煙を燻らせながら、普段と変わらないぞんざいな彼女の応えに、寧ろ安心感さえ芽生えてくる。
「だって、お礼がまだでしたし~」
「ホンル君の言う通りなり」追随するようにしてイサンはようやく口を開く。「私からも礼を言わせなむ。……二人とも、此度はかたじけなし」
「礼の一つを寄越すくらいなら、一件でも多く俺に整理業務を割り振るよう掛け合ってくれよ」
俺はより多くの芸術と出会いたいだけだからな――煙を吐き出しながら続けられた彼女の言葉は、どこまでも自分自身に正直だった。まあ、そこが彼女らしいと言えばらしいのだが。
「あは、どういたしまして~。それにしても……ん~……気が抜けたら一気に小腹が空いてきちゃいました」伸びの動作に合わせて時計を見上げる。就業時間はとっくに過ぎていた。「折角ですし、このまま何か食べに行きませんか?」
そう言って、覗き込んだイサンの丸みを帯びた瞳にあえかな光が宿る瞬間を見た。まさか、本当に誘われるとは夢にも思っていなかったのだろうか。接してみてようやく気付いたことだが、確かにほとんど表情に変化は見られないとはいえ、彼は存外に驚きやすく、動揺しやすい。
「あ、もしかしてこのまま帰ろうって思ってました? え~……僕、夕食を食べに行こうって約束したじゃないですか~。酷いなあ」
その証拠として、いっそわざとらしく頬を膨らませると、慌てふためくイサンの挙動が面白くて、思わず噴出しそうになるのを何とか堪える。
「あ、あれや演技ならざりける?」
「演技じゃないですよ~。今、演技じゃなくなりました」
子どもの屁理屈だが、このまま別れるには惜しい――もう少しだけ、彼と話してみたいと思ってしまったことは確かだ。
「勿論、良秀さんもご一緒しますよね?」
「おいイサン、断っていいぞ。俺も帰るからな」
「そんな~。僕と良秀さんの仲じゃないですか~」
「気・悪・言。叩き斬るぞ?」
いつも通りの言葉の応酬。ただ、いつもと違うことがあるとすれば。
「…………ふふ、」
その中に、堪えきれずにとうとう零れ落ちた笑声が一つ、混じったことくらい。
――それはきっと、これから何かが芽吹く予兆。
畳む
#LCB61 #W社
束縛/ホンイサ
ぽんぽん派とセブン協会
おもむろにベッドから身を起こしたイサンが、無造作に床へと放り出された下着を拾い上げる。一夜の耽溺に身を委ねた後の彼は、酷くそっけない。閨を共にした相手を起こそうともせず――まあ、すでに自分が起きていることくらいはお見通しなのだろうけれど――目覚めのキスすら交わしてくれることなく、手早く身支度を整えるとまるで気ままな風のように、颯とこの場を立ち去ろうとしてしまうのだから。
「……イサンさんって」彼の細腰にしっかと腕を回し、無防備な肩へと顎を載せる。ほんの少しだけ、丸みを帯びた瞳孔が此方を見た。
「体にたくさんベルトを着けてますよね~」
見下ろせば、眼前に覗く足――無防備に晒された白い下腿とは対照的な黒の靴下を固定するように巻かれたベルトへ指を滑り込ませる。これだけではない。ベルトを引き抜き、スラックスを剥ぎ取った瞬間、太腿に食い込むベルト――イサン曰く「シャツガーター」というらしい。彼らしいといえば彼らしいが、遅々とした動作で金具にベルトにと外されていくものだから、だいぶ据え膳を食らわされてたことだけは覚えている――が視界に飛び込んできた時は、危うく思考を放棄しかけた。
「イサンさん、あまりこういうのを着けてるイメージがないというか~」
さして長くもない交流でこそあったとして、少なくともイサンという男は「見目を気にする」ような人柄とは対極にあるように思える。決してだらしがないというわけではないけれど、暴漢の鎮圧中にジャケットが返り血まみれになったところで、さほど気に留めることなく自分と面会するような彼が、はたしてたかがシャツの乱れ程度で頓着するだろうか。
「もしかして~……僕に会うからって張り切っちゃいました?」
「……寝言は寝て言いたまえ」
「あっ、酷い。人が折角勇気を出して聞いたのに~」
さめざめと目元を手で覆ったところで、慰めるような素振りも一切見せない――さすがに泣き真似くらいではすぐに看破されるか。
「装いしこそ動きやすければ」
なるほど。見目重視ではなく、飽くまで活動的機能性に重きを置いているならば、まだ納得出来るか。
そんな色気の「い」の字もないような男が、昨夜は自身と同じ男に組み敷かれ、普段の落ち着いた低音からは想像出来ぬほどの蕩めく高音を漏らしては、蹂躙されるがままにその扇情的な色香を際限なく咲かせていたのだから、人とは底知れないものだと改めて実感する。
「……さて、いつまでかくしたらむとすや?」
「ん~?」
自分よりも肉付きの悪い華奢な身を抱き竦めたまま、小首を傾げながら彼の言葉を吟味する――ああ、そろそろ離せと言いたいのか。
「う~ん……離してあげてもいいんですけど~……」
ふいと、床に放り出されたままの紐状のそれを一瞥して。
「……あれ、僕に着けさせてくれません?」
「イサンさんって、外勤をしてる割には細いですよね~。あまり筋肉がつかない方だったりします?」
なめらかな流線を描く太腿を撫ぜながら、口を衝いて出た言葉にイサンは僅かに目を細めた。
「この都市におきて、見目ほど信用に値せぬものやなからぬ?」
「まあ、仰る通りで~……あ、締め付けはきつくないですか?」
外骨格、生体施術、刺青、義体――等々。金さえあれば、この都市では身体強化を行う手段などごまんとある。もしかすると、目の前にいる彼も刺青の類でもどこかに入れているのだろうか。ふつふつと込み上げてくる好奇心を抑えるように、長さを調整したベルトを太腿に巻き付けた。
「今少しばかりゆとりを……うむ、さばかりに」
次は、ベルトから伸びる紐、その先端にある金具でシャツに一つ一つ挟んでいく。存外に緩めになったので問題ないのか疑問を抱いたものの、彼曰くこのくらいが動きやすいらしい――シャツの合間からちらちらと見切れる赤い鬱血痕。白皙に映える一等鮮やかなそれに、昨日の情事の余韻に思いを馳せつつ、左右それぞれ三つずつ、頭上から降り注ぐ言葉を頼りにようやく留め終えたそれがスラックスの下に消えていく様を最後まで見届けた。
「ほらほら、腕を出してくださ~い」
後は、アームバンドで袖丈を調整し、鼻歌交じりで皺を伸ばしておいたジャケットを羽織らせたところでようやく身支度が完了する。ネクタイと襟元を直していた指先で、まるで愛玩動物にするかのように擽ってやった白い喉元が、ふるりと震えた。
「ん、……?」
「ねえ、イサンさん。ベルトをたくさん身に着けている人って、束縛願望があるんだそうですよ?」
線を描くようにして首をなぞる――そう。それはまるで、彼に似合う枷でも思い描くかのように。
「……今度は、首輪でも用意しましょうか。イサンさん、黒がよく似合うと思うんですけど――」
イサンさんは、どんな首輪がいいと思います?
そうして、丁寧に結び直した布の上へと唇を落とした。
彼と再び相まみえることになる――確信めいた予感こそあったけれど、以前の賭けからしばらくして、彼が再び自分のもとに現れた時は心が舞い上がるほどの喜びに打ち震えたことを今でも覚えている。
彼とは様々な遊戯に興じた。ポーカー、チェス、将棋――そのどれにおいても彼は聡明で、これまでに挑んだ誰よりも強い。慢心する猶予すら与えてもらえなくて、危うく何度も負けそうになったけれど、持ち前の運と度胸でジャックポットを掴んでいった。
勝利の報酬として、唇を要求したことがある。震えながらも味わったそれはあたたかく、僅かに珈琲の味がした。
時には手を繋いで共に買い出しに出掛けたこともあった。贈った茶を喜んでもらえたならばいいのだけれど。
そして昨日は――彼のぬくもりを求めた。
彼は、拒絶はしなかった。
以前、確かに自分は言った。どうしても捜査に行き詰まったり、困ったりした時はいつでもここに来てくれと。与えた情報の報酬はまた「遊びにでも付き合ってくれればそれで良い」――と。
そう、自分との遊びに付き合いさえすれば、条件は達成される。
それ以外に提示された条件など、単なるきまぐれだ。生真面目に応じる必要はどこにもない――というのに、そうであるにもかかわらず、イサンは決してそれ等の条件を無視することはしなかった。
イサンという男は泰然自若として、何者にも縛られない。
けれど、彼は気付いているだろうか?
あたかも、目には見えない枷に繋がれでもしているかのように。
無自覚のうち、自分の下した命令に縛られていることに。
――けれど、きっと。誰よりも固執しているのは。
こうでもしなければ、彼を縛ることは出来ないと思っているのは。
イサンがいなくなった自室。柔らかくて広々としたベッドの上で、小さく膝を抱き寄せながら微かに残された熱の残渣に触れる。彼に繋がれた透明な鎖へと口付けするかのように、ホンルは熱を帯びた指先へと、切に唇を落とした。
畳む
#LCB61 #ぽんぽん派 #セブン協会
ぽんぽん派とセブン協会
おもむろにベッドから身を起こしたイサンが、無造作に床へと放り出された下着を拾い上げる。一夜の耽溺に身を委ねた後の彼は、酷くそっけない。閨を共にした相手を起こそうともせず――まあ、すでに自分が起きていることくらいはお見通しなのだろうけれど――目覚めのキスすら交わしてくれることなく、手早く身支度を整えるとまるで気ままな風のように、颯とこの場を立ち去ろうとしてしまうのだから。
「……イサンさんって」彼の細腰にしっかと腕を回し、無防備な肩へと顎を載せる。ほんの少しだけ、丸みを帯びた瞳孔が此方を見た。
「体にたくさんベルトを着けてますよね~」
見下ろせば、眼前に覗く足――無防備に晒された白い下腿とは対照的な黒の靴下を固定するように巻かれたベルトへ指を滑り込ませる。これだけではない。ベルトを引き抜き、スラックスを剥ぎ取った瞬間、太腿に食い込むベルト――イサン曰く「シャツガーター」というらしい。彼らしいといえば彼らしいが、遅々とした動作で金具にベルトにと外されていくものだから、だいぶ据え膳を食らわされてたことだけは覚えている――が視界に飛び込んできた時は、危うく思考を放棄しかけた。
「イサンさん、あまりこういうのを着けてるイメージがないというか~」
さして長くもない交流でこそあったとして、少なくともイサンという男は「見目を気にする」ような人柄とは対極にあるように思える。決してだらしがないというわけではないけれど、暴漢の鎮圧中にジャケットが返り血まみれになったところで、さほど気に留めることなく自分と面会するような彼が、はたしてたかがシャツの乱れ程度で頓着するだろうか。
「もしかして~……僕に会うからって張り切っちゃいました?」
「……寝言は寝て言いたまえ」
「あっ、酷い。人が折角勇気を出して聞いたのに~」
さめざめと目元を手で覆ったところで、慰めるような素振りも一切見せない――さすがに泣き真似くらいではすぐに看破されるか。
「装いしこそ動きやすければ」
なるほど。見目重視ではなく、飽くまで活動的機能性に重きを置いているならば、まだ納得出来るか。
そんな色気の「い」の字もないような男が、昨夜は自身と同じ男に組み敷かれ、普段の落ち着いた低音からは想像出来ぬほどの蕩めく高音を漏らしては、蹂躙されるがままにその扇情的な色香を際限なく咲かせていたのだから、人とは底知れないものだと改めて実感する。
「……さて、いつまでかくしたらむとすや?」
「ん~?」
自分よりも肉付きの悪い華奢な身を抱き竦めたまま、小首を傾げながら彼の言葉を吟味する――ああ、そろそろ離せと言いたいのか。
「う~ん……離してあげてもいいんですけど~……」
ふいと、床に放り出されたままの紐状のそれを一瞥して。
「……あれ、僕に着けさせてくれません?」
「イサンさんって、外勤をしてる割には細いですよね~。あまり筋肉がつかない方だったりします?」
なめらかな流線を描く太腿を撫ぜながら、口を衝いて出た言葉にイサンは僅かに目を細めた。
「この都市におきて、見目ほど信用に値せぬものやなからぬ?」
「まあ、仰る通りで~……あ、締め付けはきつくないですか?」
外骨格、生体施術、刺青、義体――等々。金さえあれば、この都市では身体強化を行う手段などごまんとある。もしかすると、目の前にいる彼も刺青の類でもどこかに入れているのだろうか。ふつふつと込み上げてくる好奇心を抑えるように、長さを調整したベルトを太腿に巻き付けた。
「今少しばかりゆとりを……うむ、さばかりに」
次は、ベルトから伸びる紐、その先端にある金具でシャツに一つ一つ挟んでいく。存外に緩めになったので問題ないのか疑問を抱いたものの、彼曰くこのくらいが動きやすいらしい――シャツの合間からちらちらと見切れる赤い鬱血痕。白皙に映える一等鮮やかなそれに、昨日の情事の余韻に思いを馳せつつ、左右それぞれ三つずつ、頭上から降り注ぐ言葉を頼りにようやく留め終えたそれがスラックスの下に消えていく様を最後まで見届けた。
「ほらほら、腕を出してくださ~い」
後は、アームバンドで袖丈を調整し、鼻歌交じりで皺を伸ばしておいたジャケットを羽織らせたところでようやく身支度が完了する。ネクタイと襟元を直していた指先で、まるで愛玩動物にするかのように擽ってやった白い喉元が、ふるりと震えた。
「ん、……?」
「ねえ、イサンさん。ベルトをたくさん身に着けている人って、束縛願望があるんだそうですよ?」
線を描くようにして首をなぞる――そう。それはまるで、彼に似合う枷でも思い描くかのように。
「……今度は、首輪でも用意しましょうか。イサンさん、黒がよく似合うと思うんですけど――」
イサンさんは、どんな首輪がいいと思います?
そうして、丁寧に結び直した布の上へと唇を落とした。
彼と再び相まみえることになる――確信めいた予感こそあったけれど、以前の賭けからしばらくして、彼が再び自分のもとに現れた時は心が舞い上がるほどの喜びに打ち震えたことを今でも覚えている。
彼とは様々な遊戯に興じた。ポーカー、チェス、将棋――そのどれにおいても彼は聡明で、これまでに挑んだ誰よりも強い。慢心する猶予すら与えてもらえなくて、危うく何度も負けそうになったけれど、持ち前の運と度胸でジャックポットを掴んでいった。
勝利の報酬として、唇を要求したことがある。震えながらも味わったそれはあたたかく、僅かに珈琲の味がした。
時には手を繋いで共に買い出しに出掛けたこともあった。贈った茶を喜んでもらえたならばいいのだけれど。
そして昨日は――彼のぬくもりを求めた。
彼は、拒絶はしなかった。
以前、確かに自分は言った。どうしても捜査に行き詰まったり、困ったりした時はいつでもここに来てくれと。与えた情報の報酬はまた「遊びにでも付き合ってくれればそれで良い」――と。
そう、自分との遊びに付き合いさえすれば、条件は達成される。
それ以外に提示された条件など、単なるきまぐれだ。生真面目に応じる必要はどこにもない――というのに、そうであるにもかかわらず、イサンは決してそれ等の条件を無視することはしなかった。
イサンという男は泰然自若として、何者にも縛られない。
けれど、彼は気付いているだろうか?
あたかも、目には見えない枷に繋がれでもしているかのように。
無自覚のうち、自分の下した命令に縛られていることに。
――けれど、きっと。誰よりも固執しているのは。
こうでもしなければ、彼を縛ることは出来ないと思っているのは。
イサンがいなくなった自室。柔らかくて広々としたベッドの上で、小さく膝を抱き寄せながら微かに残された熱の残渣に触れる。彼に繋がれた透明な鎖へと口付けするかのように、ホンルは熱を帯びた指先へと、切に唇を落とした。
畳む
#LCB61 #ぽんぽん派 #セブン協会
博戯に秘す/ホンイサ
ぽんぽん派とセブン協会
「はい、これがご所望だった情報です」
さも当たり前のように眼前に提示された紙束を見つめる。一向に受け取る気配のない相手を不思議に思ったのだろうか。満面の笑みを、どこか童めいた面持ちに変えて、向かい合う青年はきょとんと首を傾げた。
「……あ、もしかして偽物だって疑ってます? それなら、ゆぅっくりと吟味してくれて構いませんよ~」
そうして、半ば強引に握らされたそれの表紙へと、気が進まないながらも手を伸ばす。ぽんぽん派――何度聞いても巫山戯た名だが、これでもれっきとしたJ社裏路地のカジノを牛耳るマフィアの一つだ――の傘下にある組織によって密かに売買されているという違法薬物の入手および流通経路の詳細、顧客名簿、等々。情報の正確性については実際に調査、精査してみない限りはいかんとも言い難いが、中には慎重を期すためにも公にしていないはずの――自身も情報収集に携わった売人達のリストまでご丁寧に纏められていて、虚偽と切り捨ててしまうにはあまりに内容が緻密過ぎた。
「……確かに、私の欲せし情報と違わず」
「ふふっ、なら良かったです~。中々の力作でしょう?」
だが――それならば、なおのこと理解に苦しむと言わざるを得ない。
「これでは、そなたの言出でし条件と矛盾せずや?」
条件。そう、条件。多少のリスクを冒してでも意図的にぽんぽん派の目につくように行動したのも、連行されるようにして赴いた本拠地でマフィアのボスとの賭けポーカーの誘いに応じたのも、全ては意味があってのことだ。
自分が勝てば、傘下組織の情報が手に入る。
ボスが勝てば、曰く「僕の好きにさせてもらいます」――有り体に言えば、拒否出来ない絶対条件を一つ、己に対して提示するつもりなのだろう。
明らかに釣り合いの取れていない条件だが、それでも探し求めていた情報を前にしてどうして背を向けられようか。
結果として、自分は賭けに負けた。しかし、負けたにもかかわらず、賭けの報酬は確かにこの手の内にある。
「あ~……」間延びした、暢気な声を上げながらボスは続ける。「僕が勝ったら、好きにさせてもらうと言ったでしょう? だから『好き』にさせてもらいました」
それが当然の行いであるかのように、あっけらかんとした微笑を湛えながら言うのだから、その言葉の真意を咀嚼するまでに些かの時間を要してしまった。
一寸して、ようやく自分が彼の手のひらで転がされていたのだと悟る。
「……始めより、セブン協会に情報を渡さむとせりや」
「ご明察」
色違いの目を細める美しい男は、たおやかに笑みを深めた。
おそらく、この件に関しては我々が調査するよりもずっと前から、内々で調査を進めていたのだろう。ぽんぽん派が手中に置いている組織の情報を易々と口外するとは思っていない。そんなことをしてしまえば折角の資金源を失うことになる上、情報漏洩への関与をまっさきに嫌疑の目を向けられるリスクを鑑みたならば、当然と言えば当然だろう。ましてや今回の自分のように、何処ぞより紛れ込み、周囲を嗅ぎ回っている「ネズミ」は迅速に片付けてしまった方が組織にとっても益だろうに――まあ、手荒な真似をしてきたその時は、こちらも相応の対処を講じてでも本拠地の在所を吐かせるつもりだったが――彼はそうしなかった。
「――彼の組織を潰す気かね?」
その理由に対する解答は明白だった。
「あいつら、さすがにやり過ぎましたからね~」
首を竦めながら、仰々しい嘆息が一つ、零れ落ちる。
「調査した限りだと、一部の巣の連中にまで蔓延し始めているみたいですし……このまま放置して、頭や爪に目を付けられでもしたら大変じゃないですか。でもあからさまに自分達が調べました~ってばれても、それはそれで面倒ですし?」
それならば、敢えて他の組織が調査し、事実を白日の下に晒してしまった方がヘイトを他者へ逸らすことが出来る。加えて、晴れてぽんぽん派は裏切者を粛清するための「口実」を得られるという仕組みだ。
「別に勝とうが負けようが、どちらでも良かったんです……あっ、別にあなたを貶してるわけじゃないですよ? 寧ろ、久々に楽しくって……ついつい本気を出しちゃいました」
どこまでも悪意のない笑顔で告げた男の手が、やにわに頬へと触れる。まるで水のようにひやりと冷たい感触。誘導されるがまま、見据えた双眸は笑っているように見えて、その奥底には捕らえた獲物を逃がさんとばかりに爛爛とした輝きを宿していた。
「……それよりも、良かったんですか? こんなに簡単に提案を飲んじゃって。僕が望めば、あなたの首を飛ばすことだって……四肢をバラバラにして、死ぬより苦しい目に遭わせることだって出来たんですけど?」
そんなんじゃ長生き出来ませんよ。するりとなぞるようにして滑り落ちた指先が、喉元を捉えた。真綿で包むように緩やかに、潰れたまめとたこで厚くなった、想像していたよりもずっと硬い彼の皮膚が、徐々に首の肉へ食い込んでいく。瞬きが出来ない。許されていないから。
「っ、……然らば、地に還りしその時まで、知識を蓄積するのみよ」
「わぁ、惚れ惚れするような返事をありがとうございます~」
感嘆を乗せた言葉は、どこまでも空虚な響きだった。
「……でも、僕がいかさまをしているとか、考えもしなかったんですか?」
いかさま。囁くように紡がれた単語を脳裏に反芻しながら、テーブルに残されたままのトランプに今一度、視線を向ける。彼が何を意図してそのようなことを口にしたのか、その真意までは計り知れない――それでも、確信をもって断ずることは出来た。
「そなたは如何なる不正もしたらざらむ」
刹那、捕食者めいた眼差しがきょとんと丸みを帯びた。同時に緩められた拘束を離れ、ちょうど彼の座っていた椅子、そのすぐ傍らに置かれたままの彼の手札を見下ろす。ストレートフラッシュ――どのカードを注意深く観察し、直に表面を触れてみたところで、案の定目印になりそうな傷は一つたりとも見当たらない。
勿論、最初から疑わなかったと言えば嘘になる。実際、ぽんぽん派の構成員がカードを切る「ふり」をしている姿をこの目で目撃している。ボスに勝利をもたらすべく用意された山札――それを崩したのは、他でもないボス本人だった。彼は山札に手を伸ばすと、おもむろにそれを何度も何度も、念入りにシャッフルし始めたのだ。構成員達の反応を見るに、誰しも想定していなかった出来事なのだろう。
周囲の思惑から外れ、勝敗の決まりきった出来高レースではなく、張り詰めた緊張感の中でどちらが勝つとも分からぬ、互いの心理と心理、運と運がぶつかり合う戦場。
――その中で、今回は自分に少しばかり運が足りなかっただけだ。
「随分はっきりと言い切りますね」
「違うや?」
「それは……う~ん、ご想像にお任せします」
曖昧な応えを返した青年の笑みが、心なしか晴れやかなあどけなさを孕んでいるように思えたのは、果たして自分だけだろうか。一歩、一歩とまた近付く足音。伸ばされた指先が、幾許かの優しさをもって頬を撫ぜる。
「渡した情報の使い道についてはお任せします。……それと、どうしても行き詰まったり、困ったりした時はいつでもここに来てください。お代は……そうだな~……またポーカーにでも付き合ってくれれば、それで良いので」
さらりと音を立て、揺らめいた黒絹が頬に触れる。高価な宝石とも見紛うような双眸に見入られたまま――あたたかい何かが口唇に触れ、すぐに離れていった。
「ふふっ、次にまた会える日を楽しみにしてますよ――『イサン』さん」
何の気なしに紡がれた自身の名。
――はて、自分は彼の前でこの名を一度でも口にしたことがあったろうか。
* * *
「……あのさぁ」
あのイサンとかいうセブン協会のフィクサーがここを去った後、無断でいかさまを働いた者達の「後始末」を終えてソファで寛いでいた彼が、どこか遠くを見つめるような眼差しで柔らかな湯気を立てる水面――ボスは酒よりも茶を好んで飲用する傾向があった――を眺めながら、不意打ちのように口を開く。
「運命って信じる?」
「は……う、運命ですか?」
やたらシリアスな口ぶりだと思えば、ボスの口からそのようなメルヘンな単語が出てくるとは想像もしなかった。思わず噴出しそうになるのをぐっと堪える。ここで笑ってしまえばどうなるか、火を見るよりも明らかだったからだ。
ボスによると、最近似たような夢を見るのだという。見たことのない場所で、時には見知った場所で、自身を管理人だとのたまう時計頭に指示されながら、自分と同じように指示を受ける者達と共に見たことのない化け物と戦う夢――その中で、あのフィクサーと同じ顔、同じ声、そして同じ名を持つ青年と相まみえたことがあるらしい。
「扱っていたのはナイフだったし、こっちの彼より幼く見えたけど」そう、付け加えながら。「なんだか面白くてさ、つい話してみたくなったんだよね~」
戦闘の合間にどのような会話があったとか、その際に浮かべた表情がどうだったとか、夢の中で起きた出来事を楽しげに語るボスは、どこか楽しげで。
「……それ、まるで恋でもしているみたいじゃないですか」
思わず、口を衝いて出た言葉を呑み込もうとしたが、もう遅い。
「恋、かぁ……そうだな~」
鳩が豆鉄砲でも食らったかのような顔でこちらを凝視していたボスの口元が、しかし先程の失言など気にする素振りも見せず、ゆるり弧を描く。緩慢な動作でシャンデリアから大窓に見える裏路地の夜景へと細めた視線を移したその人は茶杯を呷ると、薄ら濡れた自身の唇をそ、といとおしげになぞって。
「……また会いたいなぁ」
ぽつり、甘やかな呟きを空に溶かした。
畳む
#LCB61 #ぽんぽん派 #セブン協会
ぽんぽん派とセブン協会
「はい、これがご所望だった情報です」
さも当たり前のように眼前に提示された紙束を見つめる。一向に受け取る気配のない相手を不思議に思ったのだろうか。満面の笑みを、どこか童めいた面持ちに変えて、向かい合う青年はきょとんと首を傾げた。
「……あ、もしかして偽物だって疑ってます? それなら、ゆぅっくりと吟味してくれて構いませんよ~」
そうして、半ば強引に握らされたそれの表紙へと、気が進まないながらも手を伸ばす。ぽんぽん派――何度聞いても巫山戯た名だが、これでもれっきとしたJ社裏路地のカジノを牛耳るマフィアの一つだ――の傘下にある組織によって密かに売買されているという違法薬物の入手および流通経路の詳細、顧客名簿、等々。情報の正確性については実際に調査、精査してみない限りはいかんとも言い難いが、中には慎重を期すためにも公にしていないはずの――自身も情報収集に携わった売人達のリストまでご丁寧に纏められていて、虚偽と切り捨ててしまうにはあまりに内容が緻密過ぎた。
「……確かに、私の欲せし情報と違わず」
「ふふっ、なら良かったです~。中々の力作でしょう?」
だが――それならば、なおのこと理解に苦しむと言わざるを得ない。
「これでは、そなたの言出でし条件と矛盾せずや?」
条件。そう、条件。多少のリスクを冒してでも意図的にぽんぽん派の目につくように行動したのも、連行されるようにして赴いた本拠地でマフィアのボスとの賭けポーカーの誘いに応じたのも、全ては意味があってのことだ。
自分が勝てば、傘下組織の情報が手に入る。
ボスが勝てば、曰く「僕の好きにさせてもらいます」――有り体に言えば、拒否出来ない絶対条件を一つ、己に対して提示するつもりなのだろう。
明らかに釣り合いの取れていない条件だが、それでも探し求めていた情報を前にしてどうして背を向けられようか。
結果として、自分は賭けに負けた。しかし、負けたにもかかわらず、賭けの報酬は確かにこの手の内にある。
「あ~……」間延びした、暢気な声を上げながらボスは続ける。「僕が勝ったら、好きにさせてもらうと言ったでしょう? だから『好き』にさせてもらいました」
それが当然の行いであるかのように、あっけらかんとした微笑を湛えながら言うのだから、その言葉の真意を咀嚼するまでに些かの時間を要してしまった。
一寸して、ようやく自分が彼の手のひらで転がされていたのだと悟る。
「……始めより、セブン協会に情報を渡さむとせりや」
「ご明察」
色違いの目を細める美しい男は、たおやかに笑みを深めた。
おそらく、この件に関しては我々が調査するよりもずっと前から、内々で調査を進めていたのだろう。ぽんぽん派が手中に置いている組織の情報を易々と口外するとは思っていない。そんなことをしてしまえば折角の資金源を失うことになる上、情報漏洩への関与をまっさきに嫌疑の目を向けられるリスクを鑑みたならば、当然と言えば当然だろう。ましてや今回の自分のように、何処ぞより紛れ込み、周囲を嗅ぎ回っている「ネズミ」は迅速に片付けてしまった方が組織にとっても益だろうに――まあ、手荒な真似をしてきたその時は、こちらも相応の対処を講じてでも本拠地の在所を吐かせるつもりだったが――彼はそうしなかった。
「――彼の組織を潰す気かね?」
その理由に対する解答は明白だった。
「あいつら、さすがにやり過ぎましたからね~」
首を竦めながら、仰々しい嘆息が一つ、零れ落ちる。
「調査した限りだと、一部の巣の連中にまで蔓延し始めているみたいですし……このまま放置して、頭や爪に目を付けられでもしたら大変じゃないですか。でもあからさまに自分達が調べました~ってばれても、それはそれで面倒ですし?」
それならば、敢えて他の組織が調査し、事実を白日の下に晒してしまった方がヘイトを他者へ逸らすことが出来る。加えて、晴れてぽんぽん派は裏切者を粛清するための「口実」を得られるという仕組みだ。
「別に勝とうが負けようが、どちらでも良かったんです……あっ、別にあなたを貶してるわけじゃないですよ? 寧ろ、久々に楽しくって……ついつい本気を出しちゃいました」
どこまでも悪意のない笑顔で告げた男の手が、やにわに頬へと触れる。まるで水のようにひやりと冷たい感触。誘導されるがまま、見据えた双眸は笑っているように見えて、その奥底には捕らえた獲物を逃がさんとばかりに爛爛とした輝きを宿していた。
「……それよりも、良かったんですか? こんなに簡単に提案を飲んじゃって。僕が望めば、あなたの首を飛ばすことだって……四肢をバラバラにして、死ぬより苦しい目に遭わせることだって出来たんですけど?」
そんなんじゃ長生き出来ませんよ。するりとなぞるようにして滑り落ちた指先が、喉元を捉えた。真綿で包むように緩やかに、潰れたまめとたこで厚くなった、想像していたよりもずっと硬い彼の皮膚が、徐々に首の肉へ食い込んでいく。瞬きが出来ない。許されていないから。
「っ、……然らば、地に還りしその時まで、知識を蓄積するのみよ」
「わぁ、惚れ惚れするような返事をありがとうございます~」
感嘆を乗せた言葉は、どこまでも空虚な響きだった。
「……でも、僕がいかさまをしているとか、考えもしなかったんですか?」
いかさま。囁くように紡がれた単語を脳裏に反芻しながら、テーブルに残されたままのトランプに今一度、視線を向ける。彼が何を意図してそのようなことを口にしたのか、その真意までは計り知れない――それでも、確信をもって断ずることは出来た。
「そなたは如何なる不正もしたらざらむ」
刹那、捕食者めいた眼差しがきょとんと丸みを帯びた。同時に緩められた拘束を離れ、ちょうど彼の座っていた椅子、そのすぐ傍らに置かれたままの彼の手札を見下ろす。ストレートフラッシュ――どのカードを注意深く観察し、直に表面を触れてみたところで、案の定目印になりそうな傷は一つたりとも見当たらない。
勿論、最初から疑わなかったと言えば嘘になる。実際、ぽんぽん派の構成員がカードを切る「ふり」をしている姿をこの目で目撃している。ボスに勝利をもたらすべく用意された山札――それを崩したのは、他でもないボス本人だった。彼は山札に手を伸ばすと、おもむろにそれを何度も何度も、念入りにシャッフルし始めたのだ。構成員達の反応を見るに、誰しも想定していなかった出来事なのだろう。
周囲の思惑から外れ、勝敗の決まりきった出来高レースではなく、張り詰めた緊張感の中でどちらが勝つとも分からぬ、互いの心理と心理、運と運がぶつかり合う戦場。
――その中で、今回は自分に少しばかり運が足りなかっただけだ。
「随分はっきりと言い切りますね」
「違うや?」
「それは……う~ん、ご想像にお任せします」
曖昧な応えを返した青年の笑みが、心なしか晴れやかなあどけなさを孕んでいるように思えたのは、果たして自分だけだろうか。一歩、一歩とまた近付く足音。伸ばされた指先が、幾許かの優しさをもって頬を撫ぜる。
「渡した情報の使い道についてはお任せします。……それと、どうしても行き詰まったり、困ったりした時はいつでもここに来てください。お代は……そうだな~……またポーカーにでも付き合ってくれれば、それで良いので」
さらりと音を立て、揺らめいた黒絹が頬に触れる。高価な宝石とも見紛うような双眸に見入られたまま――あたたかい何かが口唇に触れ、すぐに離れていった。
「ふふっ、次にまた会える日を楽しみにしてますよ――『イサン』さん」
何の気なしに紡がれた自身の名。
――はて、自分は彼の前でこの名を一度でも口にしたことがあったろうか。
* * *
「……あのさぁ」
あのイサンとかいうセブン協会のフィクサーがここを去った後、無断でいかさまを働いた者達の「後始末」を終えてソファで寛いでいた彼が、どこか遠くを見つめるような眼差しで柔らかな湯気を立てる水面――ボスは酒よりも茶を好んで飲用する傾向があった――を眺めながら、不意打ちのように口を開く。
「運命って信じる?」
「は……う、運命ですか?」
やたらシリアスな口ぶりだと思えば、ボスの口からそのようなメルヘンな単語が出てくるとは想像もしなかった。思わず噴出しそうになるのをぐっと堪える。ここで笑ってしまえばどうなるか、火を見るよりも明らかだったからだ。
ボスによると、最近似たような夢を見るのだという。見たことのない場所で、時には見知った場所で、自身を管理人だとのたまう時計頭に指示されながら、自分と同じように指示を受ける者達と共に見たことのない化け物と戦う夢――その中で、あのフィクサーと同じ顔、同じ声、そして同じ名を持つ青年と相まみえたことがあるらしい。
「扱っていたのはナイフだったし、こっちの彼より幼く見えたけど」そう、付け加えながら。「なんだか面白くてさ、つい話してみたくなったんだよね~」
戦闘の合間にどのような会話があったとか、その際に浮かべた表情がどうだったとか、夢の中で起きた出来事を楽しげに語るボスは、どこか楽しげで。
「……それ、まるで恋でもしているみたいじゃないですか」
思わず、口を衝いて出た言葉を呑み込もうとしたが、もう遅い。
「恋、かぁ……そうだな~」
鳩が豆鉄砲でも食らったかのような顔でこちらを凝視していたボスの口元が、しかし先程の失言など気にする素振りも見せず、ゆるり弧を描く。緩慢な動作でシャンデリアから大窓に見える裏路地の夜景へと細めた視線を移したその人は茶杯を呷ると、薄ら濡れた自身の唇をそ、といとおしげになぞって。
「……また会いたいなぁ」
ぽつり、甘やかな呟きを空に溶かした。
畳む
#LCB61 #ぽんぽん派 #セブン協会
君に落ちる孤独の融点について/ホンイサ
囚人と囚人
虫のささめきも息を潜める深き夜。耳を傾けるべき仲間達の語らいは、疾うに寝静まってしまった。鼓膜を鳴らす静寂の中、読書に耽ることすら難渋するほどの盲いたような 晦冥における唯一の暇潰しといえば、窓から覗く星彩を眺めることくらいだというのに。輝きの一粒たりとも見出せぬ、果てなく塗り潰された漆黒を仰ぎ見ては、暗々の内に零れ落ちた嘆息を夜気に溶かした。
不寝の番、長椅子に凭れたまま、一寸先さえ――己の輪郭さえも朧げな闇に身を委ねていると、もしやするとこの身はぐずぐずに融け果ててしまったのではないかという錯覚に陥る。ひとひらの光もない夜とは、ここまで心寒いものだったろうか。もはや目を開けているのか、瞑っているのかも曖昧な暗中において、触れることを許された座席の感触、硬質な硝子質の冷淡さ――抱え込んでいた自らの腕に、知らず知らず食い込む指の痛みだけが、自身が未だ人としての原型を留めているのだと教えてくれる証左となった。
思惟を途切れさせてはならない。ほんの瞬きの間でも自己を自己たりえる確固たるそれを「無」にしたが最後、ただでさえ薄弱としたこの意識は容易く呑まれ、漠然とした暗黒淵に沈むだろう。
声の出し方を忘れてしまった者の叫びなど、一体何人が聞き届けられよう。
「だ~れだ?」
両の目を覆った、柔らかなぬくもりがあった。不意打ちのように齎された自分以外の熱源に、途切れた思考は紡ぐべき言葉を見つけられずにいると、解放された視界のすぐ先で、犯人自ら浮かない面持ちで顔を覗き込んできた。
「イサンさん? 大丈夫ですか、さっきからずっとぼうっとしてますけど~」
指、何本あります? 眼前に三本の指――辛うじて、見える。先ほどまで何も見通せなかったはずなのに――を提示しながら小首を傾げている男をじい、と見つめる。
自分は、彼を知っている。
「……ホンル、くん」
「あ、気付きました? 良かったです~。近くまで来たのに全然反応してくれないから心配したんですよ~?」
脳裡に過った同僚の名を口にすると、いつもの人懐こい笑みを湛えたまま、さも当たり前のように長椅子の隣に腰掛ける青年はすらりと伸びた長い足を夜闇に悠々とぶらつかせながら、しかし心なしか優しい声色で続ける。
「何か、考え事でもしてたんです?」
――まるで、自分の考えていることは全てお見通しであると言わんばかりに。
これでは何も、だなんてとても言えなかった。
「……星に」
「うん?」
どのくらいの間、そうしていたのだろうか。おそらく瞑目していたのだろう眼瞼を上げた視界に、一等鮮やかに耀う光を見たような気がした。
「星に、会わまほし――と」
「星」反芻。ぱちり、瞬いた瞳が闇夜を仰ぐ。「……ああ、そういえば今日は全然見えませんね~」
星見ついでに星座の見方でも教えてもらおうと思ったのに、残念。そう言いながらもさほど落胆した素振りを見せない青年に、小さく頭を振る。
「されど、私の願いは叶いけり」
そうして――目の前の「星」に手を伸ばす。
指先を撫ぜた絹糸めいた漆黒はひやりと冷えていたけれど。
その先で触れた白皙の熱はじわりと、悴む指に染み入っていく。まるで溶けていくようだ――溶けてしまってもいい。
互いの息遣いすら共有出来る距離で、見つめ合う。
一瞬だけ動揺を映した双眸は、しばらくすると緩やかに細められる。
「……お目当てのものは見つかりました?」
「ああ、幸いにも態と其方より来たり」
「あははっ。……なら、もっと近くで見てもいいですよ?」
そう、戯けるように綻んだ彼の花唇に口付ける。触れるだけの接吻を一度、もう一度――一時の間を置いて、今度は彼から唇を寄せてきた。こういう時は目を瞑るのがマナーなのだと教えられていたものだから、彼が今、どのような顔をしているのか分からない――好奇心こそあったけれど、彼の矜持を暴くような禁忌を侵すのは憚られた。口付けを重ねるごとに、徐々に口唇を重ねている時間が長くなっていく。熱く蕩めくようなひと時。酸素が満足に行き渡らぬ脳髄は甘く痺れていた。
何よりも、決して離さぬとばかりに腰を掻き抱く腕の強さが――堪らなく、うれしい。
呼吸が弾み始めた頃、ようやく解放された身を、今度は強かに抱き竦められる。
「も~……何で不寝番の時に限って積極的なんですか?」
肩に埋められた彼の表情を窺うことは出来ない。
「不満なりや?」
「不満です~。こんな思いをして、この後一人で寝なきゃいけない僕の身にもなってくださいよ~」
それでも、普段に比べて余裕を欠いた彼の声色が――静寂の中だからこそ殊に、ひっきりなしに打ち慣らされる心音が、何よりも如実に彼の感情を表していて。
「……明日、皆さんが寝静まった夜に――待ってますから」
とうとう待ち焦がれた星の囁きに、年甲斐なく上気した顔をぎこちなく、しかしやおら縦に振った。
畳む
#LCB61
囚人と囚人
虫のささめきも息を潜める深き夜。耳を傾けるべき仲間達の語らいは、疾うに寝静まってしまった。鼓膜を鳴らす静寂の中、読書に耽ることすら難渋するほどの盲いたような 晦冥における唯一の暇潰しといえば、窓から覗く星彩を眺めることくらいだというのに。輝きの一粒たりとも見出せぬ、果てなく塗り潰された漆黒を仰ぎ見ては、暗々の内に零れ落ちた嘆息を夜気に溶かした。
不寝の番、長椅子に凭れたまま、一寸先さえ――己の輪郭さえも朧げな闇に身を委ねていると、もしやするとこの身はぐずぐずに融け果ててしまったのではないかという錯覚に陥る。ひとひらの光もない夜とは、ここまで心寒いものだったろうか。もはや目を開けているのか、瞑っているのかも曖昧な暗中において、触れることを許された座席の感触、硬質な硝子質の冷淡さ――抱え込んでいた自らの腕に、知らず知らず食い込む指の痛みだけが、自身が未だ人としての原型を留めているのだと教えてくれる証左となった。
思惟を途切れさせてはならない。ほんの瞬きの間でも自己を自己たりえる確固たるそれを「無」にしたが最後、ただでさえ薄弱としたこの意識は容易く呑まれ、漠然とした暗黒淵に沈むだろう。
声の出し方を忘れてしまった者の叫びなど、一体何人が聞き届けられよう。
「だ~れだ?」
両の目を覆った、柔らかなぬくもりがあった。不意打ちのように齎された自分以外の熱源に、途切れた思考は紡ぐべき言葉を見つけられずにいると、解放された視界のすぐ先で、犯人自ら浮かない面持ちで顔を覗き込んできた。
「イサンさん? 大丈夫ですか、さっきからずっとぼうっとしてますけど~」
指、何本あります? 眼前に三本の指――辛うじて、見える。先ほどまで何も見通せなかったはずなのに――を提示しながら小首を傾げている男をじい、と見つめる。
自分は、彼を知っている。
「……ホンル、くん」
「あ、気付きました? 良かったです~。近くまで来たのに全然反応してくれないから心配したんですよ~?」
脳裡に過った同僚の名を口にすると、いつもの人懐こい笑みを湛えたまま、さも当たり前のように長椅子の隣に腰掛ける青年はすらりと伸びた長い足を夜闇に悠々とぶらつかせながら、しかし心なしか優しい声色で続ける。
「何か、考え事でもしてたんです?」
――まるで、自分の考えていることは全てお見通しであると言わんばかりに。
これでは何も、だなんてとても言えなかった。
「……星に」
「うん?」
どのくらいの間、そうしていたのだろうか。おそらく瞑目していたのだろう眼瞼を上げた視界に、一等鮮やかに耀う光を見たような気がした。
「星に、会わまほし――と」
「星」反芻。ぱちり、瞬いた瞳が闇夜を仰ぐ。「……ああ、そういえば今日は全然見えませんね~」
星見ついでに星座の見方でも教えてもらおうと思ったのに、残念。そう言いながらもさほど落胆した素振りを見せない青年に、小さく頭を振る。
「されど、私の願いは叶いけり」
そうして――目の前の「星」に手を伸ばす。
指先を撫ぜた絹糸めいた漆黒はひやりと冷えていたけれど。
その先で触れた白皙の熱はじわりと、悴む指に染み入っていく。まるで溶けていくようだ――溶けてしまってもいい。
互いの息遣いすら共有出来る距離で、見つめ合う。
一瞬だけ動揺を映した双眸は、しばらくすると緩やかに細められる。
「……お目当てのものは見つかりました?」
「ああ、幸いにも態と其方より来たり」
「あははっ。……なら、もっと近くで見てもいいですよ?」
そう、戯けるように綻んだ彼の花唇に口付ける。触れるだけの接吻を一度、もう一度――一時の間を置いて、今度は彼から唇を寄せてきた。こういう時は目を瞑るのがマナーなのだと教えられていたものだから、彼が今、どのような顔をしているのか分からない――好奇心こそあったけれど、彼の矜持を暴くような禁忌を侵すのは憚られた。口付けを重ねるごとに、徐々に口唇を重ねている時間が長くなっていく。熱く蕩めくようなひと時。酸素が満足に行き渡らぬ脳髄は甘く痺れていた。
何よりも、決して離さぬとばかりに腰を掻き抱く腕の強さが――堪らなく、うれしい。
呼吸が弾み始めた頃、ようやく解放された身を、今度は強かに抱き竦められる。
「も~……何で不寝番の時に限って積極的なんですか?」
肩に埋められた彼の表情を窺うことは出来ない。
「不満なりや?」
「不満です~。こんな思いをして、この後一人で寝なきゃいけない僕の身にもなってくださいよ~」
それでも、普段に比べて余裕を欠いた彼の声色が――静寂の中だからこそ殊に、ひっきりなしに打ち慣らされる心音が、何よりも如実に彼の感情を表していて。
「……明日、皆さんが寝静まった夜に――待ってますから」
とうとう待ち焦がれた星の囁きに、年甲斐なく上気した顔をぎこちなく、しかしやおら縦に振った。
畳む
#LCB61
純愛には果てなく遠い恋慕/ホンイサ ※R-18
黒雲会と剣契
黒雲会と剣契
夜はさむいからそばにいて/イサファウ ※R-18
囚人と囚人 ※「朝に照らされるだけの生命」の続き
囚人と囚人 ※「朝に照らされるだけの生命」の続き